議論を、科学・学問の軌道にのせるために
■「位至三公鏡」
 さらに大きな問題をとりあげよう。
さらに大きな問題をとりあげよう。
それは、「位至三公鏡」問題といえるものである。
「位至三公鏡」とよばれる形式の鏡がある。
その一例(『洛陽銅鏡』上巻による)は西晋中後期 直径9.7cm、厚さ0.4cm、円形、円鈕、円鈕座。鈕座の上下にある双線の間に、それぞれ縦書きの「位至」、「三公」の4字の銘文がある。左右両側に変形鳳紋がある。外に2条の弦紋と櫛歯紋がめぐる。幅広い無紋の平縁。2003年4~7月、伊川県槐荘墓地6号西晋中後期墓出土。河南省文物考古研究院蔵[河南省文物考古研究所・伊川県文物管理委員会、2005]。(霍宏偉)右の写真参照。
すでに、この会で紹介した『洛鏡銅華』(岡村秀典氏監訳の日本語版では、『洛陽銅鏡』)には、「位至三公鏡」の類といえるものが、十二面紹介されている。いずれも「西晋」時代の鏡とされている。
西晋王朝は、「西暦265年~316年」のあいだつづいた。すなわち、卑弥呼の時代のあとの、三世紀末から、四世紀はじめごろに存在した王朝である(下図参照)。
(下図はクリックすると大きくなります)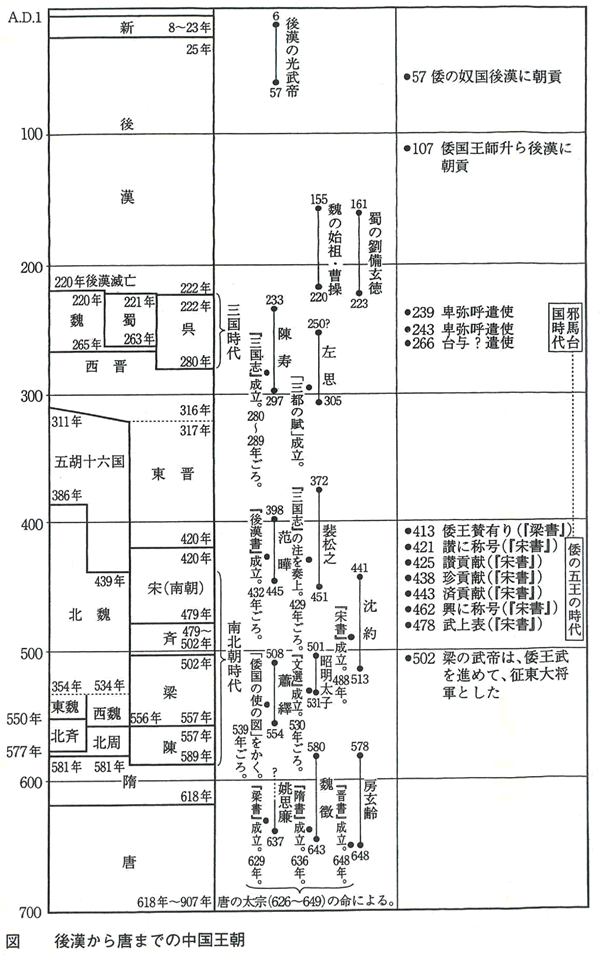
・中国出土の「位至三公鏡」の年代
中国の秦・漢時代から南北朝時代までの、洛陽付近での考古学的発掘の、報告書類を集大成したものとして、『洛陽考古集成-秦漢魏晋南北朝巻-』(上・下二巻、中国・北京図書館出版社、2007年刊)が発行されている。
また、洛陽付近から出土した鏡をまとめた図録に、さきに述べた『洛鏡銅華』(上・下二冊、中国・科学出版社、2013年刊)がある。
『洛陽考古集成』『洛鏡銅華』にのせられている「位至三公鏡」のうち、出土地と出土年のはっきりしているものすべてを、表の形にまとめれば、下の表のようになる。
(下図はクリックすると大きくなります) 
これらはすべて、魏や西晋の都であった洛陽付近から出土しているものである。
この表(洛陽付近出土の「位至三公鏡」)をみると、つぎのようなことが読みとれる。
(1)「位至三公鏡」は、後漢晩期に出現している。
(2)この表(洛陽付近出土の「位至三公鏡」)の全部で二十七面の鏡のうち、後漢時代のものは、一面のみで、魏や西晋期のものが二十六面である。圧倒的に、魏や西晋(265年~316年)の時代のものが多い。No.2~9に記すように、「洛陽晋墓」のばあい、二十四面の出土鏡のうち、八面は、「位至三公鏡」である。この表(洛陽付近出土の「位至三公鏡」)の「洛陽晋墓」のばあい、西暦287年(太康八)、295年(元康九)、302年(永寧二)の、三つの墓誌がでていることが注目される。いずれも、西晋時代のもので、西暦300年前後である。
(3)西晋よりもあとの、南北朝時代のものとしては、双頭竜鳳文鏡系の「宜官」銘翼虎文鏡が一面、北朝(385~581)の鏡として、洛陽市郊区岳家村から出土している。ただし、これは、出土年がしるされていない(この鏡のことは、『洛鏡銅華』および、『洛陽出土銅鏡』に記されている。)
「位至三公鏡」が、主として西晋時代のものであることは、洛陽付近以外から出土した「位至三公鏡」についてもあてはまる。
いま、近藤喬一(たかいち)氏の論文「西晋の鏡」(『国立歴史民俗博物館研究報告』55集、2003年刊)にのっている「紀年墓聚成」の表にもとづくとき、年代の確定できる中国出土の「位至三公鏡」は、下の表のとおりである。
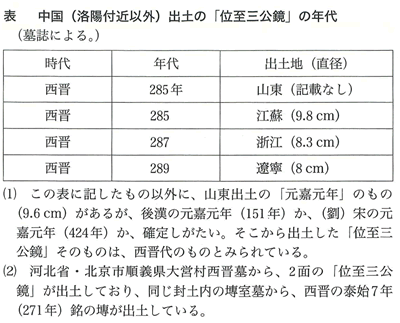 この表のものに、さきにのべた「洛陽晋墓」出土の八面の「位至三公鏡」を加えれば、年代のほぼ確定できる十二面の「位至三公鏡」のすべてが、西暦285年以後に埋納されたものといえる。すべて、西晋時代のものである。
この表のものに、さきにのべた「洛陽晋墓」出土の八面の「位至三公鏡」を加えれば、年代のほぼ確定できる十二面の「位至三公鏡」のすべてが、西暦285年以後に埋納されたものといえる。すべて、西晋時代のものである。
上の表の「洛陽付近出土の「位至三公鏡」」と「中国出土の「位至三公鏡」の年代」に示されている鏡の年代からみて、わが国から出土する「位至三公鏡」も、そのほとんどは、西暦285年以後ごろ、埋納されたもので、中国と日本との地域差、年代差を考えれば、西暦300年ごろ以後に埋納されたとみるのが穏当である。
そして、その「位至三公鏡」が、わが国においては、北九州を中心に分布している。
・わが国出土の「位至三公鏡」
「位至三公鏡」は、「三角縁神獣鏡」などと異なり、中国からも出土するが、わが国から出土する「位至三公鏡」については、つぎのようなことがいえる。
(1)中国で、おもに西晋時代に行なわれた「位至三公鏡」は、わが国では、福岡県・佐賀県を中心とする北九州から出土している。奈良県からは、確実な出土例がない(下の表参照)。
(下図はクリックすると大きくなります)
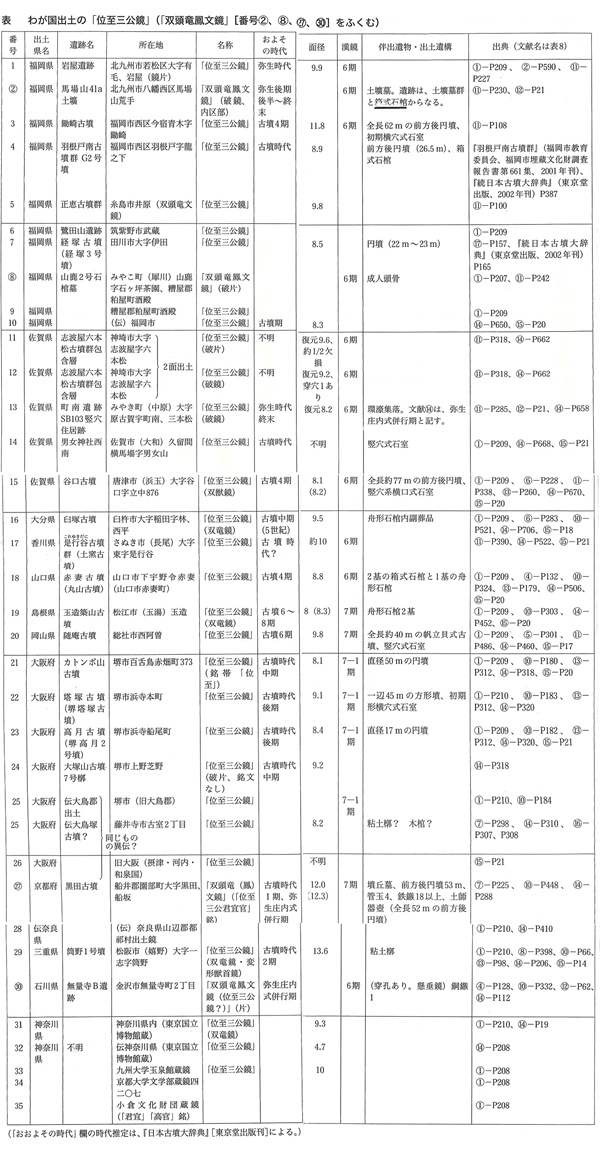
ただし、この表は、「位至三公鏡」の祖型である「双頭竜鳳文鏡」をふくむ。
(2)「位至三公鏡」よりも、形式的にまえの時代の鏡(雲雷文「長宜子孫」銘内行花文鏡など。そのなかに、魏代の鏡がふくまれているとみられる)も、北九州を中心に分布する。
(3)九州出土の「位至三公鏡」は、弥生時代の遺跡から出土しているものがあるが、九州以外の遺跡から出土した「位至三公鏡」は、まず、古墳時代の遺跡から出土している。九州以外の地の「位至三公鏡」は、九州方面からもたらされた伝世鏡か、あるいは、踏みかえし鏡であるにしても。九州よりもややのちの時代に埋納された傾向がみてとれる。
(4)これらのことから、魏のあとをうけつぐ西晋の西暦300年ごろまで、鏡の出土分布の中心は一貫して北九州にあったといえる。
(5)「位至三公鏡」よりも、形式的にも、出土状況も、あとの時代の「三角縁神獣鏡」などは、畿内、とくに奈良県を中心に分布する。(「位至三公鏡」は、おもに、庄内式土器の時代の遺物として出土し、「三角縁神獣鏡」は、おもに、そのあとの布留式土器の時代の遺物として出土する。)
(6)「三角縁神獣鏡」は、確実に三世紀の遺跡から出土例がない。四世紀の遺跡からの出土例がある。
(7)倭国は、西晋王朝と、外交関係があった。『日本書紀』の「神功皇后紀」に引用されているところによれば、西晋の『起居注』(西晋の皇帝の言行などの記録)に、西暦266年に倭の女王が晋に使いをだしたことが記されている(この倭の女王は、卑弥呼のあとをついだ台与であろうといわれている)。『晋書』にも、この年、倭人が来て入貢したことが記されている。
倭の使いが、外交関係のあった西晋の国から鏡をもたらしたとすれば、その鏡のなかには、「位至三公鏡」がふくまれていた可能性が大きい。
「位至三公鏡」などのこのような傾向からみれば、西暦300年近くまで、中国と外交関係をもった倭は、九州に存在していたようにみえる。
・「位至三公鏡」の年代
さて、問題は、ここからである。
岡村秀典氏は、その著『三角縁神獣鏡の時代』(吉川弘文館、1999年刊)のなかで、つぎのようにのべる。
「漢代四〇〇年間の鏡は、文様と銘文の流行の推移をもとに、およそ五〇年前後の目盛りでつぎのように大きく七期に区分する。
漢鏡1期(前二世紀前半、前漢前期)
漢鏡2期(前二世紀後半、前漢中期前半)
漢鏡3期(前一世紀前半から中ごろ、前漢中期後半から後期前半)
漢鏡4期(前一世紀後葉から一世紀はじめ、前漢末から王莽代)
漢鏡5期(一世紀中ごろから後半、後漢前期)
漢鏡6期(二世紀前半、後漢中期)
漢鏡7期(二世紀後半から三世紀はじめ、後漢後期)
これに三世紀の三角縁神獣鏡をはじめとする魏鏡を加え、都合、漢・三国代の中国鏡を八期に大別することにする。」
ここで、さきに、「わが国出土の『位至三公鏡』をまとめた、上の方の表[わが国出土の「位至三公鏡」(「双頭竜鳳凰文鏡」をふくむ)]を、今一度ご覧いただきたい。
この表には、「漢鏡」の欄がある。そこに、「6期」とか「7期」とか、記されている。これは、右の岡村氏の規準により、七期の区分の、どれにあたるかを示したものである。
これによれば、わが国出土の「位至三公鏡」の年代は岡村氏の区分によるとき、つぎのようになっている。
「漢鏡6期」に属するもの………………11例
「漢鏡7期」に属するもの…………………7例
(うち、「7期」とのみあるもの3例。「7-1期」とあるもの4例)
これは、岡村氏のさきの区分の年代では、「後漢中期」から「後漢後期」までのものとなる。
実年代で、「二世紀前半~三世紀はじめ」のものとなる。つまり、「卑弥呼遣使以前」の年代となる。
ところが、これは、岡村秀典氏監訳の『洛陽銅鏡』に示されている十二面の「位至三公鏡」が、いずれも、「西晋」代のものとされているのと、あきらかに矛盾する。「西晋」代は、すでにのべたように、「西暦265~316年」であって、「卑弥呼没後」の年代であるからである。
「位至三公鏡」は、岡村氏の著書によれば、卑弥呼の遣使以前のものとなり、岡村氏の監訳本によれば、卑弥呼の死後のものとなる。
なぜ、こんなことになるのか。
それは、岡村秀典氏が「景初四年鏡」をふくめ、「三角縁神獣鏡」の年代を、卑弥呼の時代のものと、きめてかかるからである。
わが国において、「位至三公鏡」の年代は、その出土遺跡や、その遺跡から出土する土器の形式からみて、(岡村氏の鏡の編年によっても、)「三角縁神獣鏡」の年代よりも、古く位置づけなければならない。
「三角縁神獣鏡」を、卑弥呼の時代のものと設定すれば、「位至三公鏡」を、それ以前の「後漢中期」から「後漢後期」のものと設定せざるをえないのである。
しかし、「事実」は、「位至三公鏡」は、おもに、西晋時代(265~316年)のものである。
「三角縁神獣鏡」は、そのあとの、主として、四世紀の、前方後円墳時代、布留式土器の時代のものなのである。
岡村秀典氏の鏡の年代論は、みずからの著書で示す年代と、監訳本のなかで示されている年代とのあいだで、矛盾している。一方では、後漢代になっているものが、一方では、西晋代になっている。監訳本のほうは、中国に原文がある。岡村氏も、大幅に内容を変更することができないのである。そのために、矛盾が生じている。前にのべた「出土」と「採集」とのくいちがいのばあいと、話の構造が同じである。
岡村秀典氏の著書の『三角縁神獣鏡の時代』のなかで示されている年代は、いろいろな異論があるなかでの、岡村氏の「推定値」「設定値」である。「西晋」時代のものとする監訳本のほうが、信頼度は高いとみられる。
・鉛同位体比の測定値
「位至三公鏡」(とくに、わが国出土の位至三公鏡)が、西晋時代以後のものとする考えをサポートする別のデータがある。「位至三公鏡」などの鉛同位体比の測定値である。
銅のなかにふくまれる鉛の同位体比によって、銅の生産地や、鏡の製作年代を、あるていどまで知ることができる。
鉛には、質量(乱暴にいえば地球上ではかったばあいの重さ)の異なるものがある。鉛は、四つの、質量の違う原子の混合物である。その混合比率(同位体比)が産出地によって異なる。
鉛には、質量数が、204、206、207、208のものがある。つまり、四つの同位体(同じ元素に属する原子で、質量の違うもの)がある。鉱床の生成の時期によって、鉛の同位体の混合比率が異なる。いわぼ、黒、白、赤、青の四種の球があって、その混合比率が産出地によって異なるようなものである。
鉛同位体比研究の重要な意味は、青銅器に含まれる鉛の混合率の分析によって、青銅器の製作年代を、あるていど推定する手がかりが与えられることである。
とくに、質量数207の鉛と206の鉛との比(Pb-207/Pb-206は鉛の元素記号をあらわす)を横軸にとり、質量数208の鉛との比(Pb-208/Pb-206)を縦軸にとって、平面上にプロットすると、多くの青銅器がかなり整然と分類される。
それによって、青銅器の製作年代などを考えることができる。
すなわち、古代の青銅器は、大きくは、つぎの三つに分類される(下図参照)。
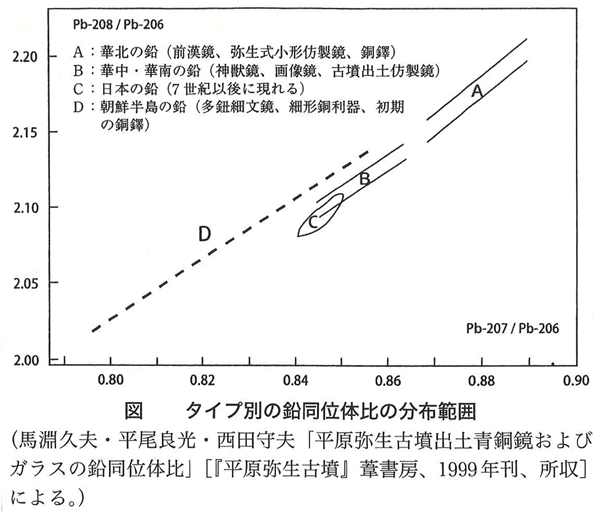
(1)「直線D」の上にほぼのるもの
もっとも古い時期のわが国出土の青銅器のデータはこの直線の上にほぼのる。「直線D」の上にのる青銅器またはその原料は、雲南省銅あるいは中国古代青銅器の銅が、燕の国を通じて、わが国に来た可能性がある。細形銅剣、細形銅矛、細形銅戈、多紐細文鏡、菱環式銅鐸などは、「直線D」の上にのるグループに属する。
「直線D」の上にのる鉛を含む青銅器を、数多くの鉛同位体比の測定値を示した馬淵久夫氏(東京国立文化財研究所名誉研究員、岡山県くらしき作陽大学教授)らは、朝鮮半島の銅とするが、数理考古学者の新井宏氏は、くわしい根拠をあげて、雲南省銅あるいは中国古代青銅器銅とする[新井宏著『理系の視点からみた「考古学」の論争点』(大和書房、2007年刊)参照]。
(2)「領域A」に分布するもの
甕棺から出土する前漢・後漢式鏡、箱式石棺から出土する雲雷文「長宜子孫」銘内行花文鏡、小形仿製鏡第Ⅱ型、そして、広形銅矛、広形銅戈、近畿式、三遠式銅鐸などは、「領域A」に分布する。弥生時代の国産青銅器の多くも、この領域にはいる。
(3)「領域B」に分布するもの
三角縁神獣鏡をはじめ、古墳から出土する青銅鏡の大部分は「領域B」にはいる。ほぼ、西暦三〇〇年ごろから四〇〇年ごろに築造されたとみられる前方後円墳から出土する鏡の多くは、この領域にはいる。
ところで、わが国で出土している「位至三公鏡」「双頭竜鳳文鏡」「蝙蝠鉦座内行花文鏡」「夔鳳鏡(きほうきょう)」など、私が、「いわゆる西晋時代鏡」とよぶものの鉛同位体比は、つぎのような重要な特徴をもつ。
参考:
・「いわゆる西晋時代鏡」にみられる鉛同位体比の特徴
(a)「位至三公鏡」「双頭竜鳳文鏡」「蝙蝠鈕座内行花文鏡」「夔鳳鏡(きほうきょう)」などの西晋時代鏡は、北九州を中心に分布する(下図参照)。
(下図はクリックすると大きくなります)
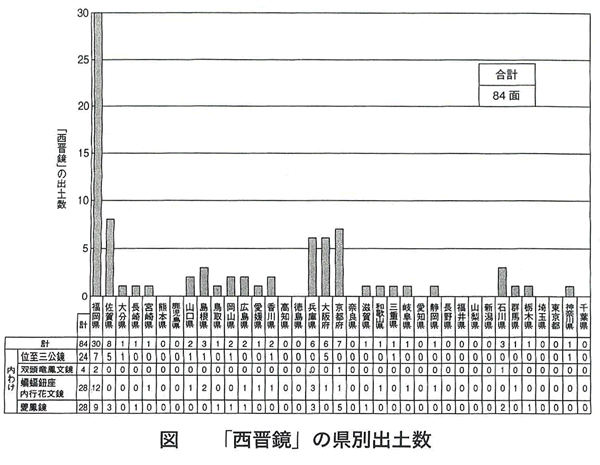
(b)これらの鏡は、中国では、おもに華北に分布する。洛陽を中心とする形で分布する。
(c)それにもかかわらず、わが国出土のこれらの鏡の鉛同位体比は、「双頭竜鳳文鏡」をふくめ、つぎの古墳時代に出土する「三角縁神獣鏡」や、「画文帯神獣鏡」などに近い。
上の方の図(タイプ別の鉛同位体比の分布範囲)の「B領域」の付近に分布する。華中・華南産の銅が用いられている。華北の銅原料ではない。つまりこれらの鏡は、それら以前の時期の中国北方系の特徴をもつ鏡と、それ以後の南方的特徴をもつ鐃との中間的・橋わたし的な特徴をもつ。文様は北方的で、原料は南方的である。
コラム1 双頭竜鳳文鏡(そうとうりゅうほうもんきょう)と位至三公鏡(いしさんこうきょう)
1.双頭竜鳳文鏡
一つの体躯の両端に竜または鳳凰の頭がついている。これを一単位の文様とするとき、二単位(二体躯分)が、左右に描かれている。
一単位の二つの頭がともに竜頭のこともあれば、一方が鳳頭のこともある。「双頭・竜鳳・文鏡」と区切るべきである。
文様の基本は、S字形または逆S字形で、点対称。
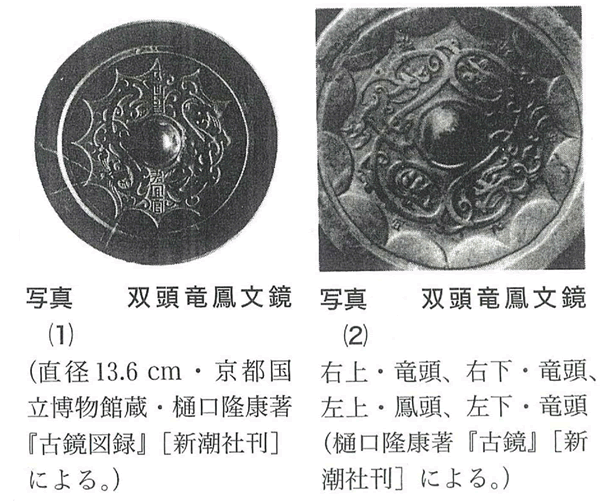
2.位至三公鏡
位至三公鏡は、「位は三公(最高の位の三つの官職)に至る」という銘のある鏡である。鈕をはさんで、上下に「位至」と「三公」の銘文をいれ、内区を二分する。
左と右とに、双頭の獣の文様を配する。獣の文様は、ほとんど獣にみえないことがある。小形の鏡である。中国では、後漢末にあらわれるが、おもに西晋時代に盛行した。
双頭竜鳳文鏡の系統の鏡である。双頭竜鳳文鏡にくらべ、獣の文様がくずれている。
また、双頭竜鳳文鏡では、主文様の外がわに連弧文があるが、位至三公鏡では、連弧文がないのがふっうである(下の写真参照)。

形式からいえば、双頭竜鳳文鏡のほうが、位至三公鏡の祖型といえる。しかし、じっさいの出土例では、双頭竜鳳文鏡が、西晋時代よりもあとの南朝時代(439~589)の遺跡から出土しているような例がある(下の写真参照)。
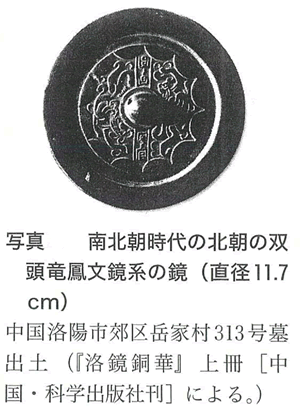
魏や晋の時代、中国の北方では、銅材が不足していた。
このことについて、中国の考古学者、徐苹芳は、「三国・両晋・南北朝の銅鏡」(王仲殊他著『三角縁神獣鏡の謎』角川書店、1985年刊所収)という文章のなかで、つぎのようにのべている。
「漢代以降、中国の主な銅鉱はすべて南方の長江流域にありました。三国時代、中国は南北に分裂していたので、魏の領域内では銅材が不足し、銅鏡の鋳造はその影響を受けざるを得ませんでした。魏の銅鏡鋳造があまり振るわなかったことによって、新たに鉄鏡の鋳造がうながされたのです。数多くの出土例から見ますと、鉄鏡は、後漢の後期に初めて出現し、後漢末から魏の時代にかけてさらに流行しました。ただしそれは、地域的には北方に限られておりました。これらの鉄鏡はすべて夔鳳鏡(きほうきょう)に属し、金や銀で文様を象嵌(ぞうがん)しているものもあり、極めて華麗なものでした。『大平御覧』〔巻七一七〕所引の『魏武帝の雑物を上(のぼ)すの疏(そ)』(安本注。ここは『上(たてまつ)る疏(そ)』と訳すべきか)によると、曹操が後漢の献帝に贈った品物の中に。金銀を象嵌した鉄鏡”が見えています。西晋時代にも鉄鏡は引き続き流行しました。洛陽の西晋墓出土の鉄鏡のその出土数は、位至三公鏡と内行花文鏡に次いで、三番目に位置しております。北京市順義、遼寧省の瀋陽、甘粛省の嘉峪関などの魏晋墓にも、すべて鉄鏡が副葬されていました。銅材の欠乏によって、鉄鏡が西晋時代の一時期に北方に極めて流行したということは、きわめて注目に値する事実です。」
西暦280年に、華北の洛陽に都する西晋の国は、華中・華南の長江流域に存在した呉の国を滅ぼす。呉の都は建業(南京)にあった。
その結果、華中・華南の銅が、華北に流れこみ、華北で、華中・華南の銅原料を用い、華北の文様をもつ青銅鏡がつくられるようになったとみられる。
西晋時代の「位至三公鏡」で、墓誌により年代の推定できるもの十二面が、すべて、西暦285年以後に埋納されたものであることは、すでに、表1、表2などでみたところである。
つまり、文様が、北方系、銅原料が華中・華南系であることは、「西晋鏡」の大きな特徴である。「西晋鏡」は、おもに呉が滅ぼされた西暦280年以後に鋳造された可能性が大きい。
それが、わが国に流れこんでいる。
・「西晋鏡」の鉛同位体比
つぎに、「位至三公鏡」「双頭竜鳳文鏡」「蝙蝠鉦座長宜子孫名内行花文鏡」「夔鳳鏡」など、おもに西晋時代に行なわれたとみられる鏡の、鉛同位体比について考える。
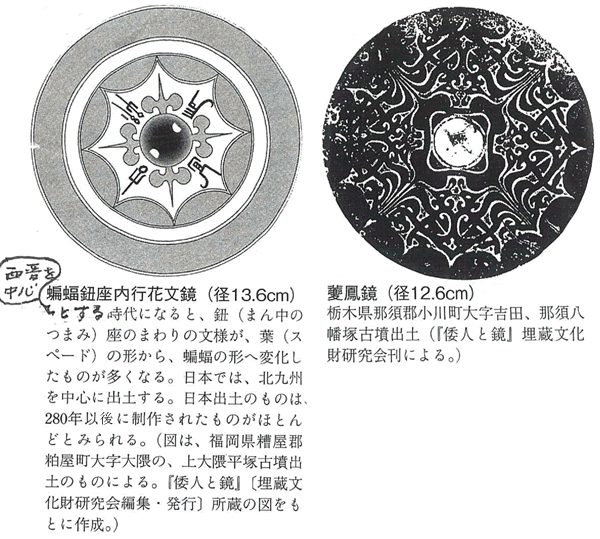
夔鳳鏡の文様の違いは下図参照
(下図はクリックすると大きくなります)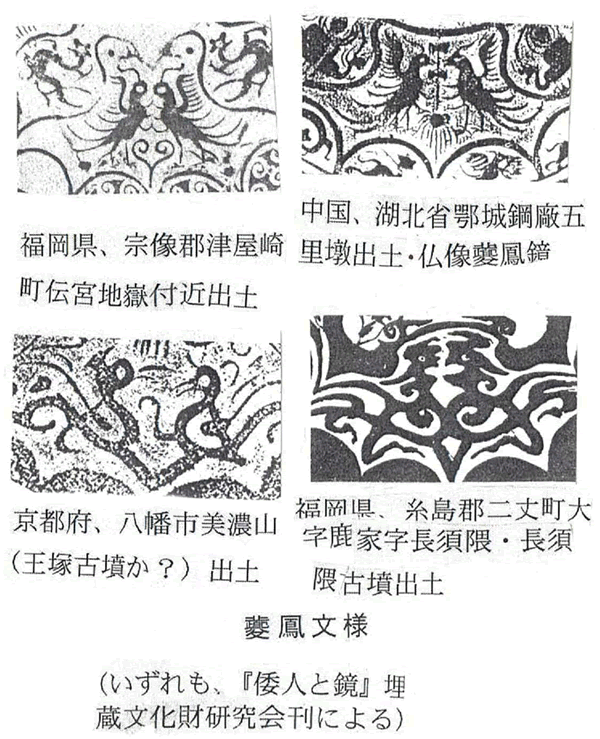
これらについては、もとのデータも、かかげておく(下の3つの表参照)。
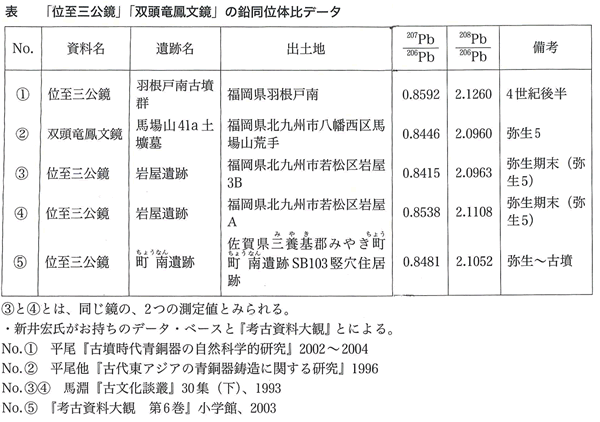
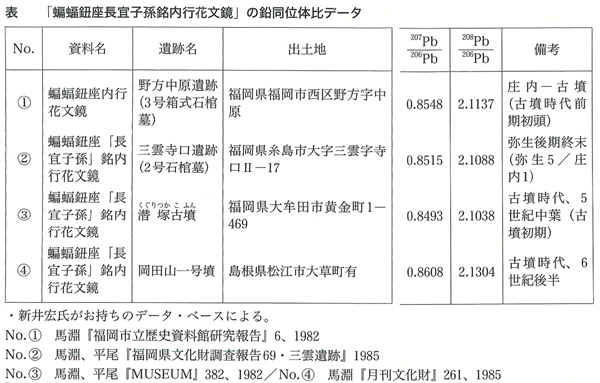
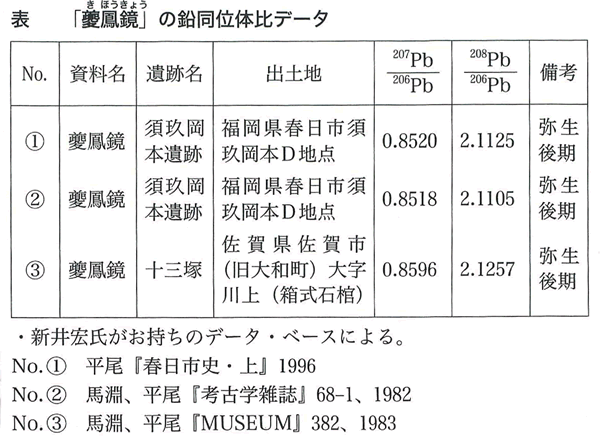
下の図をみれば、いわゆる西晋鏡の鉛同位体比は、あきらかに、それ以前のものと違っている。後漢時代の鏡とは、鉛の同位体比の分布が異なる。
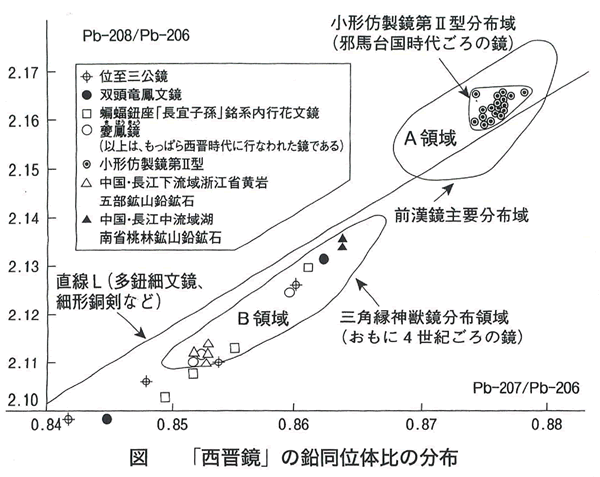
これらの鏡は、おもに、北部九州に分布しているにもかかわらず、つぎの時代に主流となる、「三角縁神獣鏡」の鉛同位体比の分布領域と、そうとうていど重なりあう。「三角縁神獣鏡」は、近畿を中心に分布する。
これらの鏡には、中国南方、長江(揚子江流域)などの「南中国」系の銅が用いられていると判断される。
上の図から、つぎのようなことがいえよう。
「『位至三公鏡』は、『双頭竜鳳文鏡』の子孫的な鏡ではある。しかし、この図をみれば、わが国出土の『位至三公鏡』と『双頭竜鳳文鏡』とで、鉛同位体比の分布に、それほど差はない。」
以上のようにみてくると、岡村秀典氏の、「位至三公鏡」などを、卑弥呼遣使以前の後漢の時代のものとする説は、自己矛盾をきたし、ほとんど完全に崩壊しているようにみえる。
国学院大学の教授であった考古学者、柳田康雄氏ものべている。
「近畿地方中央部(大阪・奈良県)では、いまだに弥生終末までに漢鏡の破片すら出土しない。岡村秀典(1999)の漢鏡の分布図では、漢鏡4期(前一世紀後葉から一世紀はじめ、前漢末から王莽代)以後近畿に分布するようになっているが、これらは伝世して早期古墳以後に副葬されるのであり、弥生時代から当該地に分布するものではなく、東漸した北部九州人が持ち込んだものである。」(『邪馬台国新聞』第5号、2017年5月22日号。【全国邪馬台国連絡協議会事務局発行】)
この柳田康雄氏の文章の意味は、重要である。
たとえば、王莽のたてた「新」 の国(西暦9年~23年)の国名のはいった「方格規矩四神鏡」は、福岡県の井原鑓溝(やりみぞ)遺跡からも出土しているし、大阪府の紫金山古墳からも出土している。
井原鑓溝遺跡から出土のものは、甕棺の副葬品で、あきらかに弥生時代のものである。これに対し、紫金山古墳のほうは、「四世紀中ごろから後半ごろの築造と考えられる」(『日本古墳大辞典』【東京堂出版刊】)のものである。
つまり、近畿地方中央部(大阪・奈良県)では、弥生時代に出土していないものが、岡村氏の分布図では、弥生時代から存在したかのように描かれているのである。
考古学者の、石野博信氏はのべる。
「墓から出てくる三角縁神獣鏡について土器で年代がわかる例を見ると、四世紀の『布留式土器』と近畿で呼んでいる土器と出てくる例はありますが、その前の、三世紀の土器と一緒に出てくる例は一つもない。それは埋葬年代を示すのであって、製作年代は示さないということはあるでしょうが、それにしても、一つもないのはおかしい。だから新しいんだろう。
つくったのは四世紀前半ぐらいだろうと思うんです。」[『邪馬台国と安満宮山古墳』 (吉川弘文館刊)]
さらに、奈良県立橿原考古学研究所の所員で、纏向遺跡を発掘し、大部の報告書『繼向』を執筆された関川尚功(ひさよし)氏は、布留式土器の初現を四世紀の中ごろとされる。
関川氏はのべる。
「布留式の初現を四世紀の真ん中前後(つまり、350年前後)」 (『三世紀の九州と近畿』河出書房新社、1986年刊)
「箸墓古墳とホケノヤマ古墳とほぼ同時期のもので、布留1式期のものであり、古墳時代前期の前半のもので、四世紀の中ごろ前後の築造とみられる。」 (『季刊邪馬台国』102号、2009年刊)
これに対し、岡村秀典氏は、つぎのようにのべる。
「日本考古学の時期区分をなるべく避けたのは、中国鏡と土器との確実な共伴関係が乏しく、それをあえて用いる必要がないこともあるが、むしろ中国の鏡と史書をもとに分析するとき、専門とする中国考古学の立場に徹してみるのが正当であり、説得力があると考えたからである。」[『三角縁神獣鏡の時代』(吉川弘文館刊)]
しかし、「三角縁神獣鏡」の多くを、中国鏡、つまり魏の皇帝からの下賜と考える岡村秀典氏の立場にたてば、その中国鏡と当時の弥生式土器との確実な共伴関係の例は、かなりな数、存在していることになるはずである。
岡村氏の論法では、三世紀の土器と一緒に出てくる例は、一つもなくても、三角縁神獣鏡は、三世紀の時代から、近畿に分布していたはずだ、ということになる。
たんに、古墳時代に至るまで、墓にうずめられる習慣がなかっただけである、ということになる。
・「奇妙な論理」
この、岡村氏の論法は、考古学者たちのとなえた次のような他の事例に近い。
(1)北九州の弥生遺跡からは、大量の鉄製品が出土する。奈良県などからは、ほとんど出土しない。これは、当時、鉄は奈良県にも存在していたのであるが、奈良県においては、土壌の性質から、サビて、溶けてなくなったのである。(この見解に対する反論。では、なぜ、四世紀以後の、古墳時代になると、奈良県からも、多量の鉄製品が、出土するようになるのか。)
(2)「三角縁神獣鏡」は、出土物としては、中国から一面も出土しない。これは、魏の皇帝が、倭のみに与えるために、特別にあつらえた「特鋳品」であるからである。
これらは、出土したデータにもとづいて帰納して得た結論ではない。あらかじめ「鉄が奈良県に存在していたこと」「三角縁神獣鏡が特鋳されたこと」を「前提」とし、そこから演繹して得た「解釈」である。「鉄が存在していた」「鏡が特鋳された」という前提じたいは、なんら証明されていない。エビデンス(証拠)は、なにも示されていない。立証責任を果していることにならない。「奇妙な論理」というべきである。
かくて、データ的事実としては、存在していないものが、存在していたことになる。
この論法における「前提」は、「想定」である。
このような「想定」が可能であるのならば、「三角縁神獣鏡」は、のちの時代に九州から持ちこんだものであるとも、のちの時代に、近畿でつくられたものであるとも、「想定」できてしまう。
「奇妙な論理」が、「説得力がある」とは、とても思えない。
土器についての情報をすてるなど、情報は切りすてれば切りすてるほど、制限条件がへり、「解釈」の可能性がふえる。よりなんでもいえることになる。自説に都合のよい結論をみちびくことができきる。
そうでなくても、わが国の考古学の方々は、「考古学的事実は、まず考古学の分野で十分考えて、」という傾向が強い。『古事記』『日本書紀』などをはじめとする文献情報や、自然科学的方法による測定値を重くみない傾向が強い。制限条件をより少なくして議論する傾向がある。
・平原遺跡出土鏡の年代
岡村氏の著書『三角縁神獣鏡の時代』は、全体的に鏡の年代が古く古くもちあげられている。たとえば、福岡県糸島市大字有田の平原遺跡出土の鏡をとりあげてみよう。
(下図はクリックすると大きくなります)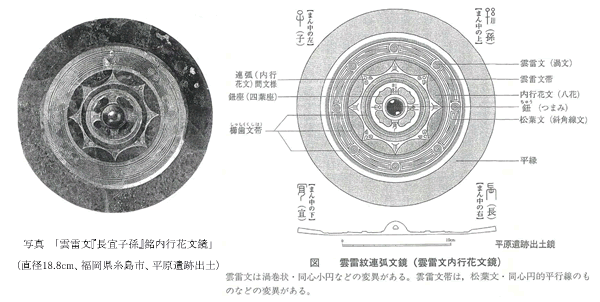
平原遺跡出土の鏡について、岡村秀典氏は、つぎのようにのべる。
「『後漢書』には五七年と一〇七年に倭人の朝貢が記録されている。平原一号墓の鏡群の年代はちょうどこの時期にあたる。鏡の製作年代は五七年の朝貢に近いが、いずれにせよ倭人の活発な朝貢が記録された時期に、それにともなって大量の漢鏡や素環頭大刀がまとまって輸入されたのである。しかも、鏡がまとまった状態で平原一号墓に副葬されているから、墓の年代も後一世紀後半からあまり下ろことはないだろう。」
「平原一号墓から出土した漢鏡5期の方格規矩神鏡の三一面には、定型化した型式のものから、方格の十二支銘が失われ、四神と瑞獣(ずいじゅう)の組合せや配置がくずれた型式のものまで含まれている。年代の下限は、後一世紀後半にある。」
「平原一号墓の年代は、その漢鏡によって後一世紀後半から二世紀初頭までと考えられ、……」(以上『三角縁神獣鏡の時代』による)
ここでは、「鏡の製作年代」から出発して、「墓の年代」まで論じられている。
ここでの文からわかるように、岡村秀典氏は、平原一号墳から出土した方格規矩四神鏡三十一面を、「漢鏡5期」の鏡であるとし、西暦紀元後一世紀後半を下限とする鏡であるという。
鏡の製作年代としては、西暦五七年に近い年代を考え、平原一号墓の築造年代としては、二世紀初頭を下限としているように読みとれる。
ところが、西暦2000年の3月に、前原市教育委員会から刊行された『平原遺跡』(「前原市文化財調査報告書」第70集)では、これらの鏡を「仿製鏡(ぼうせいきょう)」であるとし、つぎのようにのべられている。
「これらの仿製鏡の製作年代は、中国に類似品があるとすれば技術的に後漢末以後しか考えられないことから、紀元200年前後の後漢の動乱期であり、中国製品が入手困難な時期に符号する。」(福岡県教育庁文化財保護課[当時。のち国学院大学教授]の考古学者、柳田康雄氏執筆)
つまり、平原遺跡出土の方格規矩四神鏡の製作年代について、岡村秀典氏の与えた年代と、柳田康雄氏の与えた年代とでは、150年ほどくいちがう。岡村秀典氏のほうが、古くみているわけである。
すでに紹介したように、岡村秀典氏は、平原1号墓の築造年代も、「(西暦紀元)後一世紀後半からあまり下ることはないだろう」「二世紀初頭まで」とする。
柳田康雄氏は、論文「平原王墓の性格」(『東アジアの古代文化』1999年春・99号)のなかで、岡村秀典氏の論考なども検討したうえで、1998年度の確認調査の結果、平原一号墓と築造年代に大差ないとみられる平原二号墓の周溝から「古式士師器(はじき)」が発見されたことや、瑪瑙(めのう)管玉、鉄鏃などについてのくわしい考察にもとづき、平原一号墓の築造年代は三世紀前半以降としておられる。
また、福岡大学の考古学者、小田富士雄氏らも、『倭人伝の国々』(学生社、2000年刊)のなかで、つぎのようにのべておられる。
「平原(王墓)になると、これはもう邪馬台国の段階に入っています。」
平原王墓の築造年代についても、岡村秀典氏と、柳田康雄氏や小田富士雄氏らとでは、百年以上はちがう。岡村秀典氏のほうが、古くみているわけである。
岡村氏は、ほとんど鏡だけをみて年代を考えるが、柳田氏は総合的に考察している。
すくなくとも、岡村氏は、柳田氏のような実証的な考察に対し、くわしく答える必要がある。
・わが国出土の「位至三公鏡」は、西晋時代鋳造の鏡とみられる
中国社会科学院考古学研究所の所長などであった考古学者、徐苹芳はのべる。(傍線を引いたのは安本。)
「考古学的には、魏および西晋の時代、中国の北方で流行した銅鏡は明らかに、方格規矩鏡・内行花文鏡・獣首鏡、夔鳳(きほう)鏡・盤竜鏡・双頭竜鳳文鏡・位至三公鏡(いしさんこうきょう)・鳥文鏡などです。(注:三角縁神獣鏡はふくまれない)
従って、邪馬台国が魏と西晋から獲得した銅鏡は、いま挙げた一連の銅鏡の範囲を越えるものではなかったと言えます。とりわけ方格規矩鏡・内行花文鏡・夔鳳鏡・獣首鏡・位至三公鏡、以上の五種類のものである可能性が強いのです。位至三公鏡は、魏の時代(220~265)に北方地域で新しく起こったものでして、西晋時代(265~316)に大層流行しましたが、呉と西晋時代の南方においては、さほど流行してはいなかったのです。日本で出土する位至三公鏡は、その型式と文様からして、魏と西晋時代に北方で流行した位至三公鏡と同じですから、これは魏と西晋の時代に中国の北方からしか輸入できなかったものと考えられます。」(『三角縁神獣鏡の謎』角川書店、1985年刊)
この文章において、注意すべき点が二つある。
(1)日本出土の「位至三公鏡」は、中国の西晋時代の洛陽出土の「位至三公鏡」と、直径や文様などにおいて、とくに区別はつかない。下図にみられるように、中国の西晋時代の遺跡から出土のものときわめて近い型式をしたものが出土している。
(下図はクリックすると大きくなります)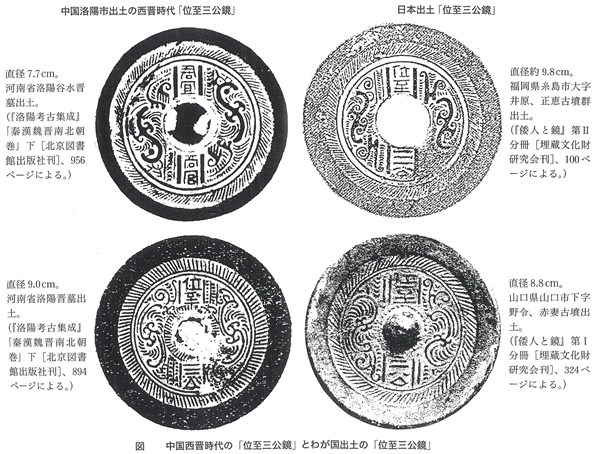
コラム2
「雲雷文長宜子孫銘内行花文鏡(うんらいもんちょうぎしそんめいないこうかもんきょう)」と「蝙蝠鈕座内行花文鏡(こうもりちゅうざないこうかもんきょう)」
「『長宜子孫』銘内行花文鏡」は、中国鏡のうちの代表的なもののひとつである。「内行花文鏡」は、内がわに、半円弧形を連環状にめぐらし、花びらを内むき(内行)につらねたような図形があるので、「内行花文」(「文」は「模様」の意味)の名がある。「『長宜子孫』銘内行花文鏡」は、後漢時代から西晋時代にかけて製作されたものが多く、中国、朝鮮、わが国の墳墓から数多く出土している。
「内行花文鏡」は、本来が、花の形であるという証拠がないため、「連弧文鏡」ということばを用いるべきだという意見がある。中国の考古学者、および、日本の中国考古学者は、ふつう「連弧文鏡」ということばを用いる。
「長宜子孫」などの文字のはいっているものを、「『長宜子孫』銘内行花文鏡」という。そして、「雲雷文」と、「雲雷文帯」のはいっているものを、「雲雷文『長宜子孫』銘内行花文鏡」という。
また、鈕(まん中のつまみ)座のまわりの文様が蝙蝠の形をしているものを「蝙蝠鈕座
『長宜子孫』銘内行花文鏡」という。
「蝙蝠鈕座『長宜子孫』銘内行花文鏡」は、ほぼかならず「長宜子孫」などの文字がはいっており、「『長宜子孫』銘内行花文鏡」の一種である。上の方にある蝙蝠鈕座内行花文鏡の写真参照)
(2)除苹芳が、魏と西晋時代の鏡としてまとめている「内行花文鏡」は、じつは、二種類に峻別することができる。
すなわち、上のコラム2で説明したつぎの二種である。
(a)雲雷文(うんらいもん)「長宜子孫(ちょうぎしそん)」銘内行花文鏡(めいないこうかもんきょう)
(b)蝙蝠(こうもり)鈕座「長宜子孫」銘内行花文鏡
(a)と(b)とは、同じく「長宜子孫」の銘をもつものでありながら、銅にふくまれる鉛の同位体比の値が大きく異なる。
(a)の、「雲雷文「名が宜子孫」銘内行花文鏡」のほうは、後漢や魏の時代の鏡とみられながら、鉛の同位体比の分布をみると、銅原料が、前代の「前漢鏡」に近く、中国北方産の銅が用いられているとみられるものである(下図参照)。
(下図はクリックすると大きくなります)
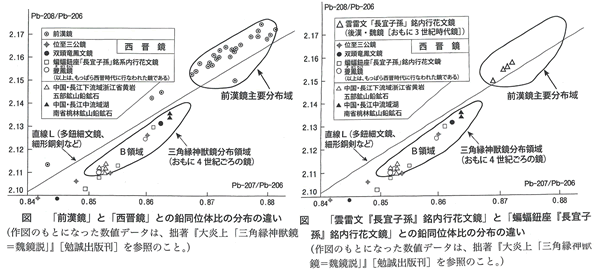
注:上に図の「『前漢鏡』と『西晋鏡』との鉛同位体比の分布の違い」で前漢鏡主要分布域の白抜き三角形は雲雷文「長宜子孫」銘内行花文鏡で、三角縁神獣鏡分布領域の白抜き三角形は中国・長江下流域浙江省黄岩五部鉱山鉛鉱石である。
一方、(b)の「蝙蝠鈕座『長宜子孫』銘内行花文鏡」のほうは、もとの呉の国の領域内で産出したとみられる銅が用いられている。
これは、西晋時代の、呉がほろびた280年以後ごろになって、はじめて洛陽付近およびわが国で普及したとみられる。
福岡県の平原遺跡から出土している「雲雷文『長宜子孫』銘内行花文鏡」なども、中国北方産の銅とみられるものが用いられている。
つまり、中国の魏晋代の遺跡から(a)や(b)の鏡が出土したならば、(a)の「雲雷文『長宜子孫』銘内行花文鏡」のほうは、大体は魏の時代の鏡で、西晋代のものとしても、呉がほろびる280年以前ごろ鋳造のものとみとめられる。
これに対し、(b)の「蝙蝠鈕座『長宜子孫』内行花文鏡」のわが国出土のものは、すべて、中国南方の、長江流域の鉛同位体比を示す。
そして、「位至三公鏡」や「双頭竜鳳文鏡」は、「蝙蝠鈕座『長宜子孫』銘内行花文鏡」とほぼ近い鉛同位体比の分布を示す。
つまり、「位至三公鏡」や「双頭竜鳳文鏡」も、中国南方の長江下流域系の銅原料が用いられている。
このような鉛同位体比を示す「位至三公鏡」「双頭竜鳳文鏡」「蝙蝠鈕座『長宜子孫』銘内行花文鏡」などは、すべて、大略。呉が滅びた280年以後の西晋時代に鋳造されたものとみられる。
「三角縁神獣鏡」は、これら「西晋鏡」のあとの、ほぼ四世紀を中心とする中国の東晋時代にあたるころ、わが国で大流行した鏡である。
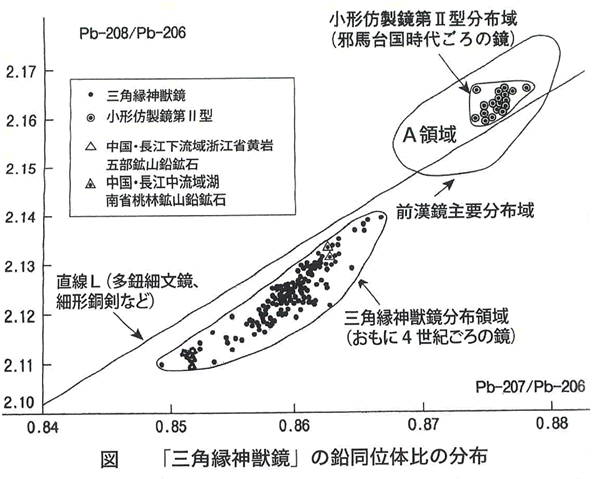
上の図の鉛同位体比の分析から長江流域の鉱山の原料が使われていると考えられる。
三国時代と東晋時代の銅鉱山の地図は下記参照。
(下図はクリックすると大きくなります)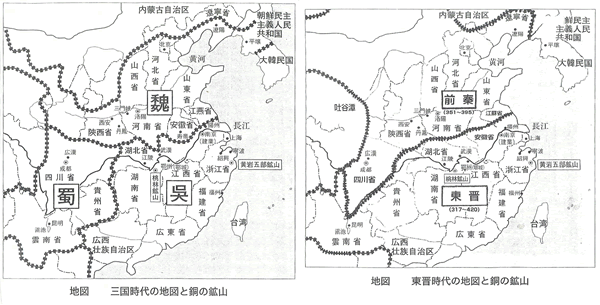
■まとめ
岡村秀典氏説のとくに大きな誤り五つ。
(1)「盖」は金属ではなく、「盖(きぬがさ)」である。
(2)「三角縁神獣鏡」は、魏から与えられた鏡ではない。(中国の学者、「棺あって槨なし」、鉛の同位体比。)
(3)「位至三公鏡」は、おもに後漢時代に製作されたものではなく、西晋時代に流行し、製作されたものである。(著書と翻訳本との矛盾。)
(4)小さな不用意な誤りが著しく多い。
(5)自説に不都合な事実、見解を全て無視している。
考古学は、今、巨大な迷路を掘っている。考古学は、魑魅魍魎(ちみもうりょう)の横行闊歩する百鬼(ひゃっき)夜行の世界となっている。非科学的、非学問的で、解体的出直しを必要とするものとなっている。







