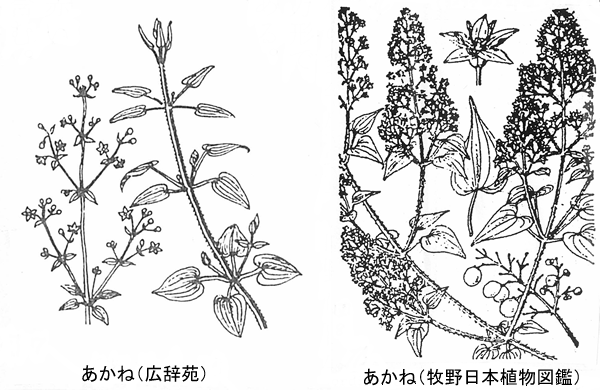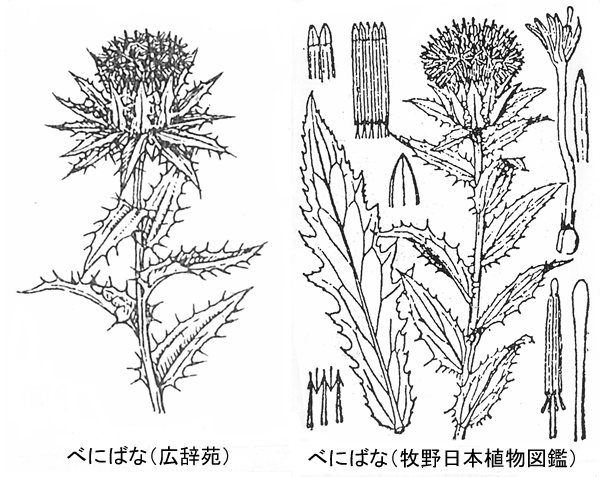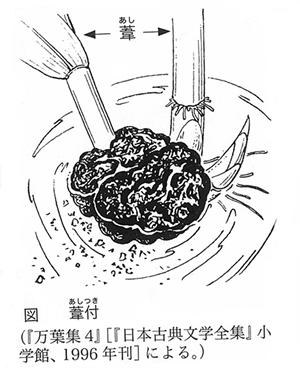■あなたはパブロフの犬にされている。
纏向遺跡から出土したものを、邪馬台国や卑弥呼と関連付けて新聞発表している。これが、続くとパブロフの犬のように、条件反射で、纏向遺跡は邪馬台国があった場所になって行く。
以下はデジタル版のニュース
読売新聞オンライン 2025.4.23
古墳時代の犬、纏向遺跡出土の骨から復元模型に・・・
犬の骨は、2015年の発掘調査で約140点が出土した。約300点あるとされる全身骨格の47%にあたる。古墳時代の犬骨の出土例は極めて少ないことから、犬の・・・
朝日新聞 2025.4.22
卑弥呼も見た「纏向犬」? 出土の骨から当時の姿・・・
女王卑弥呼(ひみこ)が治めた邪馬台国の有力候補地、奈良県桜井市の纏向(まきむく)遺跡(国史跡)で出土した3世紀前半とみられる犬の骨から、当時の姿が・・・
参考にデジタル版では無く、紙面記事を下記に示す[2025年4月23日(水)朝日新聞]
(下図はクリックすると大きくなります)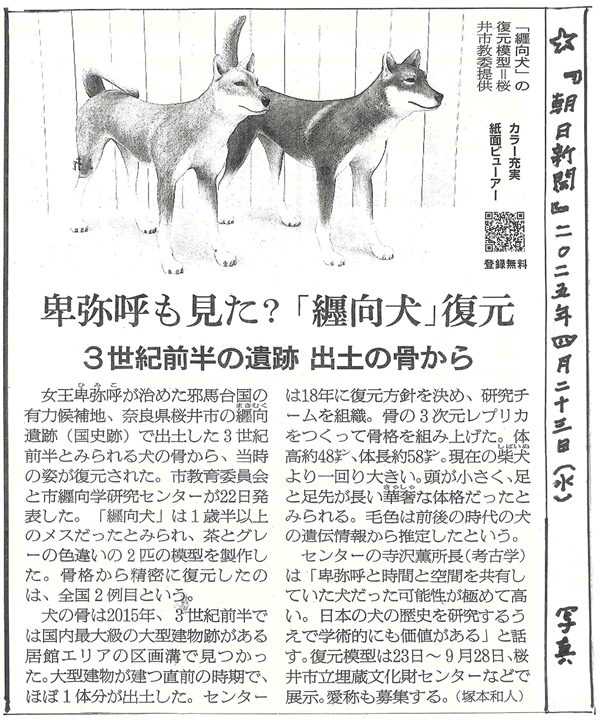
毎日新聞 2025.4.22
卑弥呼の飼い犬? 纏向遺跡から骨、復元模型の愛称・・・
全身骨格は古墳時代初頭(3世紀前半)の1歳半の雌で体高48センチ、体長58センチ。人間なら20歳ぐらいの成犬だ。いずれも天然記念物に指定されている四国犬・・・
奈良新聞 2025.4.22
きゃしゃで長い足 纏向遺跡出土の骨を元に復元模型
邪馬台国の有力候補地とされる奈良県桜井市の纏向遺跡で出土した、3世紀前半の犬の骨をもとに生体復元した模型が完成し、同市纏向学研究センターが・・・
産経ニュース 2025.4.22
「女王・卑弥呼の愛犬」を復元 宮殿跡から骨、1歳以上・・・
Yahoo!ニュース 2025.4.22
卑弥呼もなでた犬?「貴重史料」纒向遺跡で発見、出土骨・・・
このような記事で、「連想によって邪馬台国問題は解けるのか?」となる。
産経ニュース 2023.10.12
邪馬台国のゴキブリ? 奈良・纏向遺跡で世界最古・・・
朝日新聞 2023.10.13
卑弥呼も悩んでた? 奈良の遺跡から世界最古のチャバネ出土・・・
参考にデジタル版では無く、紙面記事を下記に示す[2023年10月13日(金)朝日新聞]
(下図はクリックすると大きくなります)
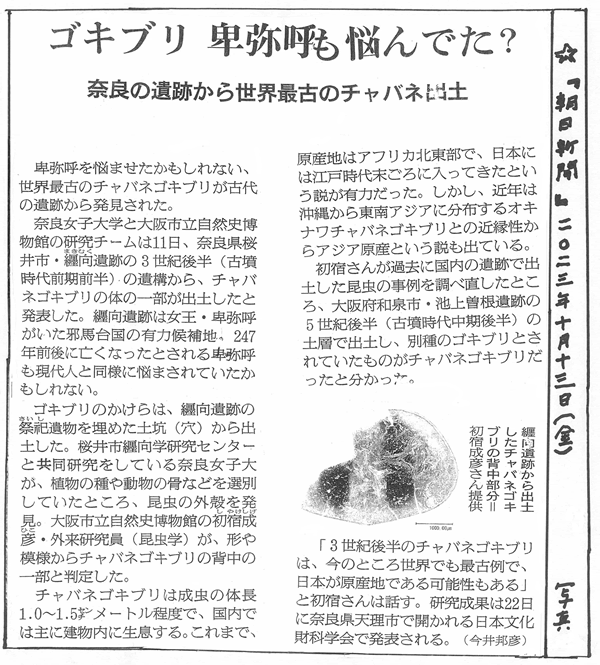
毎日新聞 2023.10.12 東京朝刊
纏向遺跡:卑弥呼の時代の「嫌われ者」世界最古?・・・
まさに、「みんなで間違える考古学。(旧石器捏造事件も)そこだと思えばそこになる方法。証明にも、科学にも、学問にもなっていない。」となっている。
毎日新聞 2018.5.14
纏向遺跡:卑弥呼時代のモモの種 邪馬台国、強まる畿内説
Yahoo!ニュース 2018.6.18
モモの種で「邪馬台国論争」終止符か
日本経済新聞 2018.5.14
卑弥呼時代の種か 年代測定で「邪馬台国=畿内」補強
参考にデジタル版では無く、紙面記事を下記に示す[2018年5月15日(火)毎日新聞]
(下図はクリックすると大きくなります)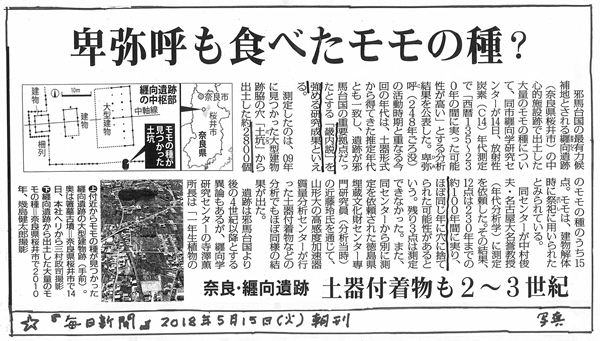
(1)桃の種のことなど、『魏志倭人伝』に記されていない。
(2)岡山県からは、もっと大量の桃の種が出土している。
上東遺跡 岡山県倉敷市から9608個の桃の種。
「論点先取(結論が先にあっての議論)」ばかり。「証明」になっていない。
『魏志倭人伝』に記載されているもので、出土量のトップを示した県のリストを示せば下記のようになる。
(但し、桃の核と大型建物は記載されていない)
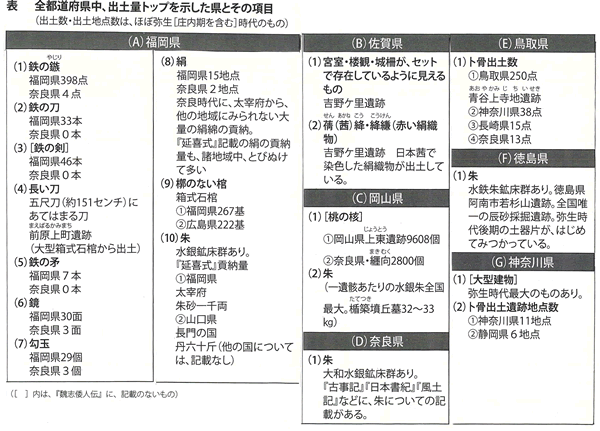
上の表から、奈良県は朱のみである。そして、朱は福岡県、岡山県、徳島県でも出土している。データではこのような状況なのに、
・奈良県には、スポットライトのあてすぎ。
・瑠璃も玻璃(はり)も照らせば光るである。
■ホケノ山古墳は卑弥呼の時代とする問題点
(1)ホケノ山古墳の築造年代推定値の中央値(メディアン)は西暦364年である(前回「邪馬台国の会第430回講演(2025年5月18日)資料参照)。卑弥呼の時代よりも百年以上のちである。
(2)寺沢薫氏の提出の資料でも、ホケノ山古墳には「木槨」があることになる。これは『魏志倭人伝』の倭人の葬制「棺あって槨なし」と合わない。「槨」があるのは、のちの古墳時代の。葬制である。
≪寺沢薫氏の資料≫
(a)寺沢薫氏による庄内様式期の出土鏡で、ホケノ山古墳から、画文帯神獣鏡などが出している。
(下図はクリックすると大きくなります)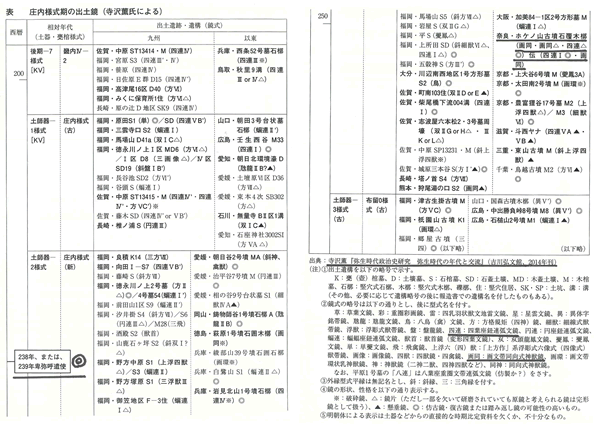
(b)寺沢薫氏の著書『卑弥呼とヤマト王権』の50ページから。
「纒向遺跡で唯一、埋葬施設の発掘がおこなわれた纒向型のホケノ山古墳は、葺石をもつ三段築成であったし、埋葬施設も北頭位であった。木槨(もっかく)を囲む石囲いは定形型の石槨(せっかく)の祖型とみることもできるし、副葬品の中国鏡や多数の鉄製品も定形型のもつ画一性と大差ない。
そもそも定形型といえども、竪穴式(たてあなしき)石槨に割竹形木棺(わりだけがたもっかん)をしつらえ、中国鏡と鉄製品・玉類を多数副葬する前方後円墳が、箸墓古墳の時期にどれほどあるだろうか。」
(3)ホケノ山古墳からは、庄内式のつぎの時代の布留式土器の時代の指標となる小形丸底土器が出土している。ホケノ山古墳は、完全に古墳時代の築造とされている。
(4)ホケノ山古墳から「画文帯神獣鏡」が出土している。わが国出土の「画文帯神獣鏡」は、鏡にふくまれる鉛の同位体比による分析の結果では、長江流域の銅が用いられている。
長江流域の銅が、わが国にはいるのは、三国時代の呉の国が、280年に西晋の国によって滅ぼされて以後に起きた現象とみられる。
じじつ、「画文帯神獣鏡」はしばしば「三角縁神獣鏡」とともに、同じ古墳から出土している。そして、寺沢薫氏は「三角縁神獣鏡」を庄内様式期よりもあとの時代の古墳としている。また、庄内様式期の鏡は、県別出土の分布では、「福岡県中心タイプ」の分布を示す。
(下のグラフ参照)
(下図はクリックすると大きくなります)
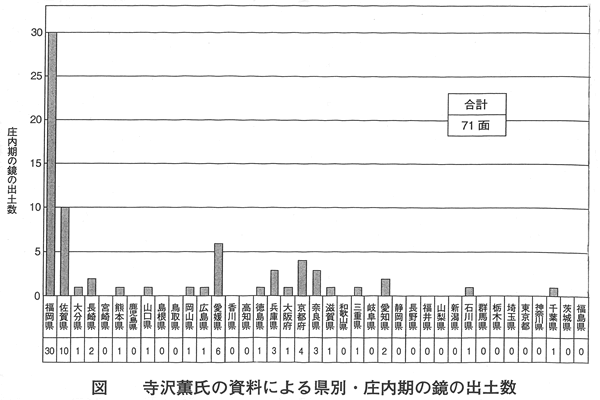
それに対し、「画文帯神獣鏡」は「三角縁神獣鏡」と同じく、「奈良県中心タイプ」の分布を示す。
分布のタイプが異なる。(下のグラフ参照)
(下図はクリックすると大きくなります)
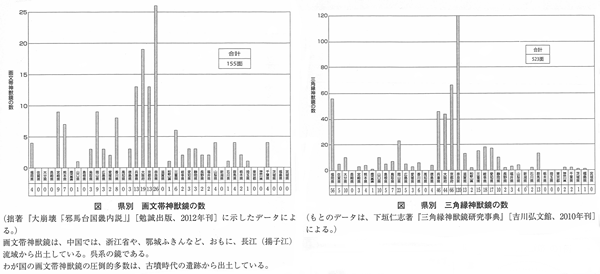
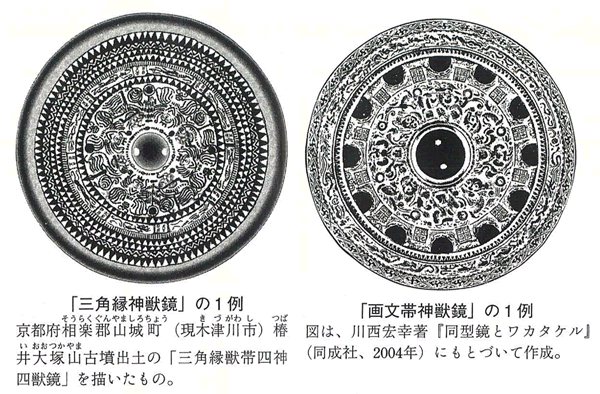
・奈良県から出土する鏡の数が0ならば、邪馬台国が奈良県に存在した確率は0となる。
・寺沢氏は、根拠のあるデータや事実を提出されているが、寺沢氏提出のデータや事実からは、寺沢氏の主張する結論は出てこない。(寺沢氏の結論を否定する)
・不都合な事実やデータは、無視、または主観的な理由で否定することが多い。(寺沢氏の議論)
・寺沢氏は、他説を批判するのに、しばしば「自己矛盾がある」という表現をされる。
しかし、寺沢氏の議論もまた、しばしば「自己矛盾のある」形になっている。
■ベニバナ論争
奈良県桜井市の教育委員会は、『魏志倭人伝』にみえる「絳」を、ベニバナと結びつける。しかし、「絳」は、ベニバナで染めたものではない。「茜(あかね)」で染めたものである。
誤ったなんの根拠もない議論が、マスコミを賑わしている。
桜井市の官僚学者たちによる「解釈の捏造」の典型的な事例。「解釈の捏造」の基本構造を、この事例によって考える。
・解釈の捏造
読売新聞社の記者であったジャーナリストの矢澤高太郎氏は、次のように述べる。
「新聞やテレビで大きく報道されることによって社会的な関心が高まり、遺跡の生命が守られたケースは多い。しかし、同時に弊害もまたさまざまな形で発生した。学者にとっては、地味な論文を発表する以前にマスコミで大々的に取り上げられるほうが知名度も高まり、学界内部での地位も保証される傾向が強まった。一部の学者や行政の発掘担当者はそれに気づき、狡知にたけたマスコミ誘導を行ってくるケースが多々見られるようになってきた。その傾向は、[旧石器捏造(ねつぞう)事件の]藤村(新一)氏以外には、考古学の"本場"である奈良県を中心とする関西地方に極端に多い。そして、発表という形をとられると、新聞各社の内部にも何をおいても書かざるを得ないような自縄自縛(じじょうじばく)の状況が、いつの間にか出来上がってしまった。そんなマスコミの泣き所を突く誇大、過大な発表は、関西一帯では日常化してしまっている。藤村(新一)氏は『事実の捏造』だったが、私はそれを『解釈の捏造』と呼びたい。」[「旧石器発掘捏造"共犯者"の責任を問う」(『中央公論』2002年12月号)]
2007年10月3日(水)のことである。朝刊各紙は、奈良県桜井市教育委員会の、繼向遺跡から出土したベニバナ花粉についての発表を報道した。
つぎに、『読売新聞』にのったものを紹介する。『朝日新聞』『毎日新聞』『日本経済新聞』などの各紙も、大略『読売新聞』の記事に近い内容を報道した。
(下図はクリックすると大きくなります)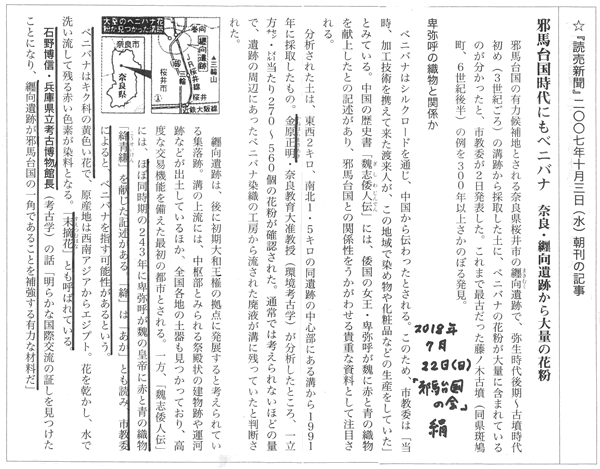
■「絳」は「べニバナ」ではなく「茜(あかね)[蒨(あかね)]」である
さきの記事のなかで、「『絳』は『あか』とも読み、(桜井)市教委によると、ベニバナを指す可能性があるという。」と記されている。そして、ベニバナであることが前提となって話が進む。しかし、「ベニバナを指す可能性がある」とする根拠は示されていない。これは、「仮説」であって、「仮説だけが上積みされている」例である。
この「絳」は、「ベニバナ」ではない。「茜(あかね)」である。
以下に、「絳」は「茜」である根拠を記す。桜井市の教育委員会は、せめて、以下にのべるていどの、「絳」を「ベニバナ」とする根拠を示してほしい。
(1)『魏志倭人伝』では、「絳青縑」という語のでてくるすぐ前のところの景初二年[じっさいは、景初三年(239)とみられる]の条のところに、「蒨絳(せんこう)五十匹」という語がでてくる。「蒨(せん)」は、「茜(せん)」と同音である。呉音、漢音ともに、「セン」で、中国音は、「qiàn」(qの音は、tsに近い)である。「茜」と「蒨」とは、音も意味も同じで、「あかね」のことである。
「蒨絳」とは、「あかね草で染めたあかね」のことである。
このことは、『魏志倭人伝』の諸注釈書が、こぞって、そう記していることである。
水野祐著『評釈 魏志倭人伝』(雄山閣出版、1987年刊)においては、「蒨絳」を説明し、「『蒨』はアカネ(茜)。これからとった赤色の染料で染めた鮮かな大赤色の布地」とする(同書495ページ)。
井上秀雄他訳注の『東アジア民族史1正史東夷伝』(東洋文庫、平凡社、1974年刊)も、「蒨絳」を、「茜染(あかねぞめ)の赤色の織物」とする。
藤堂明保監修の『倭国伝』(学習研究社、1985年刊)も、「蒨[(茜(あかね)]絳(のきぬ)」と記す。
和田清他編訳『魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝』(岩波文庫)や、石原道博著『訳注中国正史日本伝』(国書刊行会刊)なども、「蒨絳」の「蒨」について、「あかね」という説明をつけている。また、紀元前二世紀ごろに、中国で成立した辞書『爾雅(じが)』の「釈草」に、「蒨は、もって絳に染めるべし。」とある。
中国で出されている世界最大級の漢字の辞書『漢語大詞典』(漢語大詞典出版社刊)の「蒨」の説明には、「茜草。根は、絳色の染料とすべし。」とある。現在、世界最大の漢字の辞書『漢韓大辞典』(韓国・檀国大学校出版部刊)も、「茜草」の項で、『集解』という文献を引いて、「今、絳を染める。」と記す。
そして、『漢語大詞典』は、西暦500年ごろに成立した中国最初の体系的な文学評論書の『文心雕竜(ぶんしんちょうりゅう)』の、つぎの文を引く。
「絳は、蒨(あかね)において生ず(絳生於蒨)。」
『魏志倭人伝』にみえる「蒨絳(せんこう)」は、「茜絳(せんこう)」と同じである。このことばの存在じたいが、「あかね」と「絳」との結びつきを語っている。
『魏志倭人伝』じたいに、「蒨絳(せんこう)[茜染(あかねぞ)めの絳(こう)(あか色)]」という語がでてくるのに、それを「紅花(べにばな)で染めた絳」とするのは、とても自然な理解ではない。ここには、小さな「解釈捏造」の虚(うそ)色の赤い花が咲いている。いや、新聞にのっているのであるから、大きな花かな。
いや、もしかしたら、……。桜井市の教育委員会の諸先生は、『魏志倭人伝』の注釈書を読んだり、「蒨」の字を、漢和辞書で引いて調べることなど、しなかっただけなのかもしれない。
とすれば、……。ごく基礎的な勉強を、なにもしない人たちが、みずからの不勉強に気がつかないまま、「短絡的な解釈」を行ない、マスコミでの発表を行なっているのかもしれない。そのような人たちに、マスコミ発表の権限が与えられているのかもしれない。とすれば、……。あとは、「沐猴(もっこう)にして冠(かん)す。」ということばを辞書で引いて、辞書を引く練習をしてみてほしい。
茜草は、アカネ科の植物である。ベニバナは、キク科の植物である。この二つの花は、別物である。
(2)『漢語大詞典』で、「絳」の字を引くと、「草名。紅に染めるのによい」として、『文選(もんぜん)』の左思の「呉都(ごと)の賦(ふ)」での使用例を示す。さらに、劉逵(りゅうき)の注の「絳は、絳草である。臨賀郡に出(いだ)す。染めるのによい。」という文を記す(引用文の原文は、中国文)。『文選』は、梁の昭明(しょうめい)太子の編集した詩文の選集である。
「呉都の賦」の作者は、左思(さし)[250?~300?]である。卑弥呼の時代に近いころに活躍した人である。「呉都の賦」は、『三都の賦』の一つで、三国時代の呉の建業のことを詠んだ賦(韻をふんだ美文)である。
『三都の賦』を書き写すために、多くの貴人たちが紙を買いあさった。それによって、「洛陽の紙価を高めることになった」ことで知られる。現在でも、「洛陽の紙価を高める」という表現は、ベストセラーを意味するために用いられる。
『三都の賦』を書いたころ、左思は無名であった。そのため、評判にならなかった。そこで、当時の名土たちに働きかけ、劉逵(りゅうき)に注をつけてもらうなどした。そのために、世に知られるようになった。
「呉都の賦」のなかには、「紫絳」という形で、「絳」の字がでてくる。劉逵は、この「絳」にさきほどの、「絳は、絳草である。臨賀郡に出す。染めるのによい。」という注をつけている。
そして、わが国の明治書院刊の「新釈漢文大系79」の『文選(賦篇)上』は、語句にくわしい説明をほどこしているが、その中の中島千秋氏の注では、「絳」を「紅色の染色として用いる茜(あかね)草」としている(同書、265ページ)。茜草は、「紅色」を出すのである。
(3)「纁(くん)」という字がある。『説文(せつもん)』に、「浅絳なり。」とある。そして、諸橋轍次著の『大漢和辞典』や、台湾で出されている『中文大辞典』に、『説文通訓定声』という文献を引いて、つぎのような説明がある。
「韋(い)[なめし皮]を、茜(あかね)草で染めるのに、一度染めるのを韎(ばつ)という。これは、みながいうところの紅である。二度染めるのを、赬(てい)という。赤黄色である。三度染めると赤になる。
ただ、四度染める絑(しゅ)にくらべると、やや浅い。それで浅絳という。」
ここでも、浅絳色を「茜草」で染める、とある。
そして、わが国の養老令(りょう)[令は、行政法など]の注釈書『令義解(りょうのぎげ)』の「衣服令(えぶくりょう)」には、
「纁(くん)[そび]」を説明して、「三度染めるのが絳である(三染絳也)」と記されている。『漢韓大辞典』で、「纁」を引くと、「李巡いう。三染してその色すでに絳となる。纁と絳とは同じである。」とある。
私は、諸種の文献にあたってしらべたが、「絳」を「ベニバナ」とする文献に、ゆきあたらなかった。
桜井市の教育委員会においては、「絳」を「ベニバナ」とするような文献資料があるのであれば、それを提示してほしい。
(4)佐賀県の吉野ヶ里遺跡から出土した絹織物は、一部の素絹(しろぎぬ)を除いては、すべて、日本茜(あかね)で染色されたものであった(『吉野ケ里遺跡』[佐賀県教育委員会編集・発行、吉川弘文館、1994年刊]522ページ)。
(5)『延喜式(えんぎしき)』は、律令(りつりょう)の施行(しこう)細則である。927年に成立した。この『延喜式』の「民部省」のところをみると、九州の大宰府からは、「絹七千疋」「茜(あかね)二千斤」(民部省下、55・63)が、中央政府に毎年貢納されることになっている。この貢納量は、各国、各地域の「絹」「茜」の貢納量の中では、とびぬけて多い。
そのため、虎尾俊哉(とらおとしや)編の『延喜式 中』(集英社、2007年刊)では、「補注」において、わざわざ、「梅村喬(うめむらたかし)[日本史学者、大阪大学名誉教授]は、中央財政において大宰府から貢進される絹へ依存する割合が高かったことを指摘している。」と記しているほどである。
ここでは、「絹」と「茜」とが結びついているようにみえる。「絹」を染めるのに、「茜」が用いられたとみられる。
インターネットで「茜(あかね)」を引くと、『コトバンク』に、「主として絹を染めるのに用いる。」とある。
また、正倉院の古裂(こぎれ)の中に、茜(あかね)で染めた緋(ひ)[目のさめるようなあざやかな赤]の綾(あや)[模様を織り出している絹織物]があるという(虎尾俊哉編『延喜式 中』「集英社刊」257ページ頭注)。
虎尾俊哉氏は、この正倉院の古裂の緋について、「染め色としては堅牢で、旧色をよく保っている。」と記している。茜で染めると、長く色があせないようである。
『延喜式』の記載は、九州の大宰府から、中央政府への貢納品を記しているのである。 『魏志倭人伝』の「絳青縑」は、倭王から魏への上献品を記しているのである。
とすれば、『魏志倭人伝』の「倭」は、九州方面を指しているようにもみえる。
『延喜式』の「民部省」の大宰府のところでは「紫(むらさき)草五千六百斤」も記されている。これも各国、各地域のなかで、最大の量である。しかし、「紅花(べにばな)」のことは記されていない。
「紅花」の貢納は、伊賀の国のみ七斤八両とされ、その他、尾張、甲斐、信濃、紀伊、越前、越中、加賀、伯耆などの二十三国については、貢納国名のみが記されている。貢納量がすくなかったことを思わせる。
なお「民部省」は、律令時代において、戸籍・租税・賦役など、全国の民政・財政を担当した省である。
『延喜式』は、のちの時代の資料ではあるが、邪馬台国が九州であるとすると、絹[縑(けん)など]」の生産も、「絳(茜)」の生産も、昔からそろっていた可能性が大きいことをうかがわせる。
これに対し、邪馬台国を畿内とすると、「絹(縑など)」がとぼしい上に、「絳(茜)」についても、のちの時代においてさえ、大宰府から貢進される茜に依存する割合が高かったのであるから、昔から生産量がそれほどでもなかったことをうかがわせる。
このようにみてくると、桜井市の教育委員会は、ほとんど何の根拠ももたないようなことを思いこみ」、または、「コジツケ」によって結びつけて、マスコミ発表をしているようにみえる。
桜井市の教育委員会の方々は、絹を、ベニバナで染めたという文献的事例、考古学的遺物としての事例などを、具体的にあげてみて欲しい。すくなくとも、すでに示した茜(あかね)で絹を染めたという事例と同じていどにあげてみて欲しい。
「公的機関による解釈捏造の考古学」ではないか・・・
■ベニバナは、何に用いられたのか
「ベニバナ」は、かならず衣類を染めるために用いられたとはかぎらない。むしろ、はじめは、おもに、女性の化粧用のものなどであったのではないか。
「ベニバナ」は、女性の化粧用のべ二や顔料として用いられた。また、絵具(えのぐ)や薬としてももちいられた。
---------------------------------------コラム--------------------------------------------------
『源氏物語』にでてくる「末摘花(すえつむはな)」--紅花(べにばな)と紅鼻(べにばな)--
ベニバナのことを、古語では、「末摘花」ともいった。
紫式部の書いた『源氏名物語』のはじめのほうの巻六に、「末摘花」の巻がある。
この「末摘花」は、女性の名である。
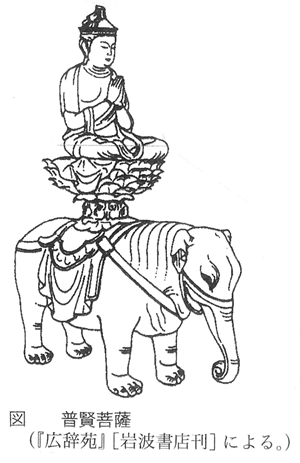 主人公の光源氏は、さる女性の手引きで、「末摘花」という名の女性とあう。
主人公の光源氏は、さる女性の手引きで、「末摘花」という名の女性とあう。
一夜をともにすごす。昔のことで、明りがない。末摘花が、どのような顔をしているのかわからない。
あくる朝、末摘花を見る。鼻が驚くほど高く長い。鼻の先が垂れていて、赤い。
紫式部の筆によれば、その鼻は、「普賢菩薩(ふげんぼさつ)の乗り物」のようであったという。
「普賢菩薩の乗り物」といえば、白い象である。
『観普賢経』という文献によれば、その白象の鼻は「紅蓮華(べにれんげ)[赤いハスの花」の色のごとし」という。
平安時代の紫式部は、動物の象の実物を見たことは、ないはずである。
おそらくは、絵か、彫り物などを見たのであろう。
光源氏は、自分の御殿(ごてん)に帰る。
御殿には、将来、自分の正妻にする予定の紫(むらさき)の君(きみ)がいる。紫の君は、まだ、十歳ほどの少女である。
光源氏は、紫の君と、絵をかいて遊ぶ。
そのとき、光源氏は、自分の鼻に、紅(べに)をぬり、紫の君にみせる。
「私の顔が、こんなになったら、どうでしょう。」
紫の君は、「いみじく笑ひ給(たま)ふ。」
「うたてこそあらめ(いやだあ)。」
「紅花(べにばな)」と「紅鼻(べにばな)」とをかけた紫式部のユーモアである。
「末摘花」という女性の名も、「最後にえらぼれる女性」、「先(さき)っちょが赤い鼻」などの意味をもたせているようにみえる。
-----------------------------------------------------------------------------------------
ここで、あかね(茜)とべにばな(紅花)について、辞書などの説明を下に示す。
「あかね」について
広辞苑から
あかね【茜】
①アカネ科の多年生蔓草。山野に自生し、根は燈色。茎は方形で中空、外部にとげがある。一節ごとに四葉を輪生し、秋、白色の花を葉腋に着生。根を染料または、通経薬・止血薬とする。茜草。
②茜の根からとった赤い染料。アリザリンを含む。茜根。
『学生版 牧野日本植物図鑑』(牧野富太郎著 北隆館)から
あかね Rubia cordifolia L. var. Mungista Miq.〔あかね科〕
山野、原野にはえるつる性の多年草。根は太く、ひげ状で黄赤色。茎はつる状で、断面は四角、逆刺がある。葉は柄があり、4枚輪生し逆刺をもつ。秋に多数の小花を密集し穂状となる。花冠は黄色で5裂し、雄しべは5。果実は黒色で球状。根を染料にあかね染といわれたものがそれである。
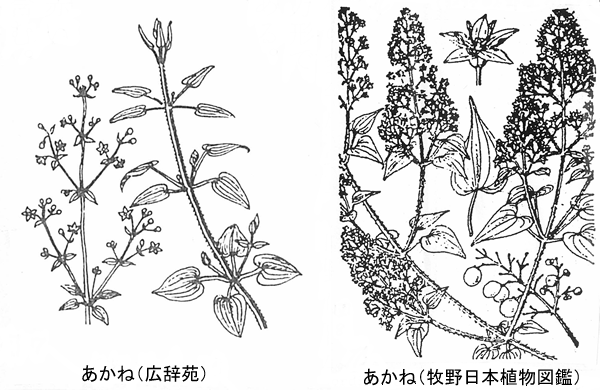
「べにばな」について、
広辞苑から
べにばな【紅花】キク科の二年草。小アジアーエジプト原産。高さ30~90センチメートル。葉は広披針形、周辺に剌がある。夏、紅黄色のアザミに似た頭花をつける。小花は細い筒形。わが国には古く中国から輸入され、東北地方を中心に栽培。花冠を採集して紅(べに)を製し、また、漢方の通経薬とする。呉(くれ)の藍。末摘花(すえつむはな)。
『学生版 牧野日本植物図鑑』(牧野富太郎著 北隆館)から
べにばな Carthamus tinctorius L.〔きく科〕
秋田県下で栽培する2年草。茎は1m位。葉は互生し、葉縁に刺がある。夏に茎の上部に紅黄色の管状の頭状花をつけ、総包片にも刺がある。古く化粧の紅の原料としたのでべにばな(紅花)とよばれ、すえつむはな、くれのあいの古名もある。
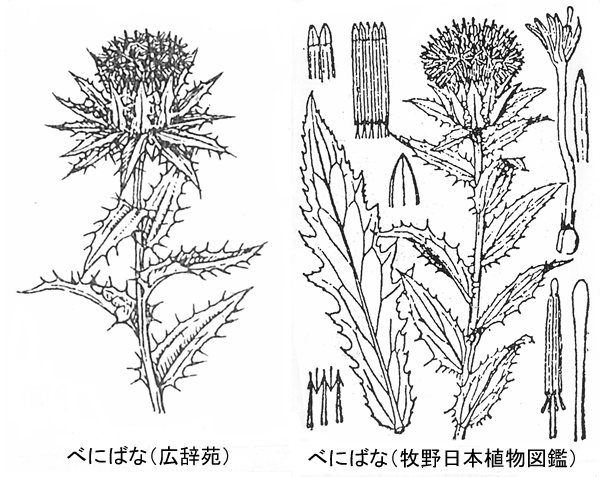
また、さきの新聞記事のなかで、公立の兵庫県立博物館館長の考古学者の石野博信(ひろのぶ)氏が「纏向遺跡が邪馬台国の一角であることを補強する有力な材料だ」と述べておられることを、記憶にとどめておいていただきたい。石野博信氏は、邪馬台国問題について、新聞などで、この種の発言をくりかえしておられる。
■もう一つの大きな問題
さて、さきの新聞記事には、さらに、もう一つの大きな問題がある。あなたは、そのことに、お気づきになられたであろうか。
この記事のなかの奈良県桜井市の纏向(まきむく)遺跡の溝跡から採取した上に、ベニバナの花粉が、大量に含まれていたことは事実とみられる。(ベニバナ出土の溝跡の年代については、議論の余地があるようにみえるが。)
しかし、この記事の、「中国の歴史書『魏志倭人伝(ぎしわじんでん)』には、倭国の女王・卑弥呼が魏に赤と青の織物を献上したとの記述があり、邪馬台国との関係性をうかがわせる貴重な資料として注目される。」あたりから話がおかしくなる。
というのは、この記事の、「赤と青の織物」とあるところは、『魏志倭人伝』では、「倭錦(わきん)・絳青縑(こうせいけん)[赤青色の、織りをつめて細かく織った絹の布]・緜衣(めんい)[まわた。絹のわたを用いた衣服]・帛衣(はくい)[白い絹の布]」とあるのである。ここに記されているのは、いずれも、絹製品である。
ところが、三世紀以前の弥生時代において、肝心の絹が出土するのは、もっぱら、北九州である。奈良県ではないのである。奈良県と『魏志倭人伝』の記事とは、簡単には、結びつかない。
考古学者の森浩一は、その著『古代史の窓』(新潮文庫、1998年刊)のなかでのべている。
「ヤマタイ国奈良説をとなえる人が知らぬ顔をしている問題がある。(中略)
布目氏[布目順郎(ぬのめじゅんろう)、京都工芸繊維大学名誉教授]の名著に『絹の東伝』(小学館、1988年刊)がある。目次をみると、『絹を出した遺跡の分布から邪馬台国の所在等を探る』の項目がある。簡単に言えば、弥生時代にかぎると、絹の出土しているのは、福岡、佐賀、長崎の三県に集中し、前方後円墳の時代、つまり四世紀とそれ以降になると奈良や京都にも出土しはじめる事実を東伝と表現された。布目氏の結論はいうまでもなかろう。倭人伝の絹の記事に対応できるのは、北部九州であり、ヤマタイ国もそのなかに求めるべきだということである。この事実は論破しにくいので、つい知らぬ顔になるのだろう。」
『朝日新聞』の記者、柏原精一(かしわばらせいいち)氏は、その著『図説・邪馬台国物産帳』(河出書房新社、1993年刊)のなかで、布目順郎の研究などを紹介したうえで、つぎのようにのべている。
「ここで、弥生時代から古墳時代前期までの絹を出土した遺跡の分布図を見てみよう。邪馬台国があった弥生時代後期までの絹は、すべて九州の遺跡からの出土である。近畿地方をはじめとした本州で絹が認められるのは、古墳時代に入ってからのことだ。
ほぼ同じ時代に日本に入ったとみられる稲作文化が、あっという間に東北地方の最北端まで広かったのとは、あまりの違いである。ヤマグワの分布は別に九州に限らないから、気候的な制約は考えにくい。
布目さんは次のような見解をもっている。
『中国がそうしたように、養蚕は九州の門外不出の技術だった。少なくともカイコが導入されてから数百年間は九州が日本の絹文化を独占していたのではないか』
倭人伝のいうとおりなら、邪馬台国はまさしく絹の国。出土品から見ても、少なくとも当時の九州にはかなり高度化した養蚕文化が存在したことには疑いがない。
『発掘調査の進んでいる本州、とくに近畿地方で今後、質的にも量的にも九州を上回るほどの弥生時代の絹が出土することは考えにくい』
そうした立場に立つなら、『絹からみた邪馬台国の所在地推定』の結論は自明ということになるだろう。」
京都大学の出身者は、伝統的に「邪馬台国=畿内説」をとる人が多いといわれる。
しかし、ここに名のみえる柏原精一氏も、布目順郎も、京都大学の出身者である。
ただ、柏原精一氏も、布目順郎も、理科系の学部の出身者である。
ものごとを、データに即してリアルにみる理科系の方の判断は、京都大学の出身の考古学者とは、また別ということであろうか。
布目順郎は、『絹の東伝』のなかで、「絹を出した遺跡の分布から邪馬台国の所在を探る」という見出しのもとに、邪馬台国の時代と、その前後の時代を通じての、絹製品出土地を、くわしく列記したうえでのべる。
「これらを通観すると、弥生後期の絹製品を出した遺跡もしくは古墳は、すべて北九州にある。したがって、弥生後期に比定される邪馬台国の所在地としては、絹を出した遺跡の現時点での分布からみるかぎり、北九州にあった公算が大きいといえるであろう。
わが国へ伝来した絹文化は、はじめの数百年間、北九州の地で醸成された後、古墳時代前期には本州の近畿地方と日本海沿岸地方にも出現するが、それらは北九州地方から伝播したものと考えられる。(中略)
ここで考えられるのは、邪馬台国の東遷のことである。私は、邪馬台国の東遷はあったと思っている。(後略)」
つまり、桜井市教育委員会の発表にもとづく記事は、「邪馬台国は奈良県にあったはずだ」という前提に立った「解釈記事」なのである。
「ベニバナ→染める→『魏志倭人伝』の赤と青の絹織物記事」という連想ゲームによる記事なのである。
しかし、この連想ゲームは、事実にもとづいていない。
ベニバナの花粉が出土したとしても、ベニバナが、かならず絹製品を染めたことにはならない。奈良県のばあい、絹以外の繊維製品を染めた可能性が大きい。当時の人々も、衣服をきていたのである。その衣服を染めただけの話であるとみられる。
ベニバナは古語では、「くれなゐ」とも、「末摘花(すえつむはな)」ともいわれた。
『万葉集』の861番の歌に、つぎのようなものがある。
「松浦川(まつらがは)川の瀬速(はや)み くれなゐの 裳(も)の裾(すそ)濡れて 鮎(あゆ)か釣るらむ」
[松浦川の、川の瀬が速いので、くれないの裳[一種の長いスカート]の裾を濡らして、娘たちは鮎を釣っていることだろうか。]
この歌に、「くれないの裳」ということばがみえる。ベニバナで染めた裳とみられる。
娘たちが鮎を釣るのに赤い絹のスカートをつけているとは思えない。これは、「からむし(苧)」か「麻」など繊維を用いた裳であろう。
ベニバナが出土したからといって、それが、『魏志倭人伝』と結びつくということにも、絹と結びつくということにもならない。
また、『万葉集』の4021番に、大伴家持(おおとものやかもち)のつぎの歌がある。 「雄神川(をかみがわ)紅(くれなゐ)にほふ 娘子(をとめ)らし 葦付(あしつき)取ると 瀬に立たすらし」[雄神川で乙女(おとめ)たちの赤い裳が陽(ひ)に映えている。その乙女らが、葦付(あしつき)(葦付ノリ。食べる川ノリの一種)を採りに、瀬に立っているらしい。]
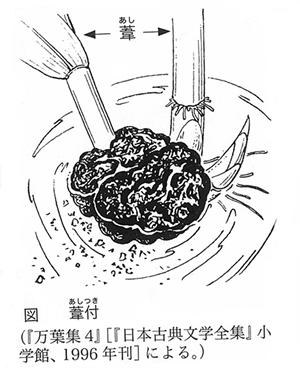
雄神川は、富山県を流れる川である。大伴家持は、越中国守であった。「葦付(あしつき)」は、早春に清流ぎわに生(は)える葦の根に発生するので、「葦付あしつき)」の名がある。大豆ぐらいの大きさに成長する。生(なま)のまま三杯酢で食べる。
養蚕は手数のかかるものである。絹はあたたかく値段も高い。だからこそ、倭から魏への献上品ともなりえたのである。
鮎を釣ったり、葦付ノリをとる娘が、絹の裳をはいているほど、絹がありふれたものであるのなら、ナイロンなどの合成繊維が発明される必要もなかったであろう。
桜井市教育委員会は、ベニバナが出土したこと以外、たしかなことをなにも言っていない。
それで、「纏向遺跡が邪馬台国の一角であることを補強する有力な材料」が、出現したことになってしまう。まったく事実無根の空想というべきである。
ほとんど「非常織」といってよい「解釈」を、しかるべき公的機関が発表し、公的機関に属する考古学者が支持し、また、新聞も、それをのせる。
ベニバナ論争のような列は、あげていけばきりがない。この種の連想ゲーム、解釈、確実な事実にもとづくとはいえない大本営発表、みずからのお国ファースト主義のフェイク(偽の)ニュースのつみかさねによって、「畿内説」は成立している。トランプのような政治家の行なうようなことを 奈良県桜井市の教育委員会が、くりかえし行なっている。
捏造をひきおこす個人、組織、文化は捏造をくりかえす傾向があるといわれている。なぜ、そのような傾向が生ずるのか。
確実な根拠をもつとはいえない「連想ゲーム」を行なっているだけなのであるが、それを発表し、宣伝するだけで、発表者や発表機関の名があがる。それで助成金がえられたり。社会的ポストが与えられたりする。その世界に住むと、それが、正しい方法にしたがっているようにみえてきてしまう。専門家ではない、不勉強なマスコミ人に、いかに、フェイク(偽の)ニュースをとりあげさせるか、に腐心する。そして、マスコミがとりあげたならば、新聞でさえみとめてくれたのであるから、正しい「証明」になっていると、思いこんでしまう。森浩一のいう「そういう所に勤めていると、つい権威におぼれ、研究がおろそかになる。」という事態が生ずる。
森浩一があえてこのように述べるのは、あまりにもいいかげんな「研究」を見すぎたためであろう。
「連想ゲーム」は簡単にできることであるから、我も我もと、同じような方法で、「連想ゲーム」を行なう。
かくて、「宣伝」と「証明」との区別のつかない世界が成立してしまっているのである。
公務員研究者は、組織を背景にもつがゆえに、簡単にマスコミに登場、発表の機会が与えられる。個人の発表であればとりあげなくても、それなりの機関の発表ということになるととりあげられる。比較的容易に発表の機会が与えられるために、挙証判断が、きわめて甘くなってしまう。
邪馬台国問題が、旧石器捏造事件に、よく似てきている。このことについては、すでに、何人かの考古学者が警告を発している。
東海大学教授の考古学者、北條芳隆(ほうじょうよしたか)氏はのべている。(傍線を引いたのは、安本。以下同じ)。
「いわゆる邪馬台国がらみでも、(旧石器捏造事件と)同じようなことが起こっている。」
「証明を抜きにして、仮説だけがどんどん上積みされており、マスコミもそれをそのまま報じている。」
「近畿地方では、古い時期の古墳の発掘も多いが、邪馬台国畿内説が調査の大前提になっているために、遺物の解釈が非常に短絡的になってきている。考古学の学問性は今や、がけっ縁(ぷち)まで追いつめられている。」(『朝日新聞』2001年、11月1日、夕刊)
明治大学の名誉教授で、日本考古学協会の会長などもされた考古学者の大塚初重(おおつかはつしげ)氏も、やはり『朝日新聞』紙上で、旧石器捏造事件にふれ、つぎのようにのべている。
「60年代以降、開発が進み、事業者の負担で何万平方メートルも一気に掘るようになる。そして、成果が出れば、日本最古だ、最大だと、マスコミがはやし立てるわけです。あげくに担当者も「時の人」として祭り上げられる。
ぼくは、あの事件(安本注・旧石器捏造事件)は、成果を求めすぎ、結論を急ぎすぎたゆえに起きたと思っています。学問にはきちんとした方法論とそれにのっとった論証、さらには議論が必要なのに、捏造事件では関係者と周囲がそれをおざなりにした。
学問は一朝一夕にはならない。結論を急いではいけないのです。かまびすしい邪馬台国の所在地論争にも今、同じことを感じています。」(『朝日新聞』2018年、7月4日、朝刊)
この、大塚初重氏の発言は、奈良県桜井市の纒向学研究センターが、2018年の5月14日に、纒向遺跡出土の桃の核(殼。種の固い部分)の、炭素14年代測定法による測定結果が、邪馬台国や卑弥呼と関係をもつかのようにマスコミ発表してから、二ヵ月たらずあとの時期の新聞にのっている。微妙で意味深長である。
そもそも、桃の核の話などは、『魏志倭人伝』に、まったく記されていない。桃の話がでてくるのは、『古事記』の出雲関係の神話のほうである。
また、岡山県倉敷市の上東(じょうとう)遺跡からは、纏向遺跡よりもはるかに多い9608個の桃の核が出土している。纏向学研究センターの発表のような議論が成立するなら、邪馬台国や卑弥の居処を、岡山県にもって行くことも、容易である。
「桃」→「不老不死の神仙思想」「魔よけの呪力」→「卑弥呼は祭祀をつかさどった」などの「連想ゲーム」「拡大解釈」によって、桃が、卑弥呼に結びつけられる。邪馬台国が纒向に結びつけられて行く。基本的には、ほとんど馬鹿馬鹿しい内容なのであるが、話としては面白いのであろう。結構マスコミを賑わしている。
朝日新聞社の記者、宮代栄一(みやしろえいいち)氏も、旧石器捏造事件に関連してのべている。
「わたしは、今回の事件(旧石器捏造事件)は、慣習と前例に頼り、職人芸的な調査や推論に次ぐ推論に頼ってきた、日本考古学界が陥った大きな落し穴であると考える。考古学は歴史を語る学問だと言いながら、わたしたちは『解釈』の方法を、理論としてシステムとして確立する作業を怠ってきた。そのつけが回ってきたのである。」
「このようなケースは旧石器時代に限らない。邪馬台国畿内説や、狗奴国の所在地論争をめぐって、恣意的な解釈や強引な主張、仮説に仮説を継ぐ議論がいかに平然と行なわれていることか。考古学の学問性は、じつは今や風前のともし火なのである。」{以上、「脆弱さを露呈した考古学---捏造発覚から1年に思う」『前期旧石器問題とその背景』[段木一行(だんきかずゆき)監修、株式会社ミュゼ、2002年刊]}
この宮代栄一氏の「推論に次ぐ推論」ということばは、さきの北条芳隆氏の「仮説だけがどんどん上積みされており」ということばと共通している。
このように、すでに、数多くの警報が発せられている。それにもかかわらず、「解釈の捏造」の方法が、あいかわらずくりかえされている。マスコミを多く賑わしているのは、現在も、むしろ、「解釈の捏造」の立場をとっている考古学者たちの言説である。
それは、旧石器捏造事件のばあいと、同じような「構造」が、現在も、存在しているからである。
旧石器の捏造を行なった藤村新一氏は、非営利法人「東北旧石器文化研究所」の副理事長であった。公的な資金が、東北旧石器文化研究所を通じて、藤村新一氏に流れるようになっていた。
藤村新一氏は、いわば旧石器の捏造を続けることによって、生計をたてていたのである。捏造を続けなければ、生活がなりたたない。そのような構造があったのである。
「解釈の捏造」の立場をとる人たちにもまた、「解釈の捏造」をつづけなければ、十分な調査費、研究費がでない、という構造がある。
『立花隆、「旧石器発掘ねつ造」事件を追う』(朝日新聞社、2001年刊)のなかで、東京大学の考古学者、安斎正人(あんざいまさひと)氏は、つぎのようにのべている。
「(旧石器を捏造した)藤村さんだけじゃなくて彼ら全体がジャーナリズムのほうに向いていましたよ。(藤村新一氏をサポートした)鎌田さん自身言っているとおり、取り上げてくれないと調査費が出ない。どれだけ広報活動するかっていうことが大事。ですから発掘したとき、学術誌に載せるよりも、メディアにいち早く出す。しかもそのメディアが、一面で書いてくれるように。」
この基本構造じたいは、邪馬台国問題のばあいも、まったく同じである。
そしてまた、異論や批判がでるごとに、新しい捏造石器や。あらたな解釈の捏造をもちだす。できるだけのマスコミ大発表を行なう。あるいは、くりかえす。これによって、異論や批判を封じこめようとする。この構造も同じである。
捏造物をもちだすことや、『魏志倭人伝』などに書かれていないものを連想や恣意的な解釈によって卑弥呼や邪馬台国に結びつけることは、簡単に、いくらでもできる。したがって、「解釈の捏造」などの種はつきない。
さきに韶介した『前期旧石器問題とその背景』の本のなかで、国士館大学の大沼克彦氏は、つぎのようにのべている。
「今日まで、旧石器研究者が相互批判を通した歴史研究という学問追求の態度を捨て、自説を溺愛し、自説を世間に説得させるためには手段を選ばずという態度に陥ってきた側面がある。
この点に関連して、私はマスコミのあり方にも異議を唱えたい。今日のマスコミ報道には、研究者の意図的な報告を十分な吟味もせずに無批判的にセンセーショナルに取り上げる傾向がある。視聴率主義に起因するのだろうが、きわめて危険な傾向である。」
これらは朝日新聞から出ている出版物にのっている見解であることが、興味をひく。
官と学による発表の形をとりながら、発表者たちの生活のため、地域おこしのための、ためにする情報もはいっていることに留意せよ。
文化庁文化財主任調査官であった岡村道雄氏はのべている。
「開発に伴って最低限遺跡の発掘記録をとるために使われている予算は平成11年度で約1100億円です。」(岡村道雄、山田晃弘、赤坂憲雄(司会)「事件が問いかけるもの---前・中期旧石器考古学の現在」[『東北学』Vol.4、2001年刊]
このほかに、博物館などの建設や維持費、大学に籍をおく研究者の助成金や人件費、その他などを加えれば、独立した個人の行なう研究などでは想像もつかない厖大な公的資金が、考古学の分野に流れこんでいる。
マスコミで、大さわぎをしている自民党のパーティ券問題や。石破首相が、お金をくばったなどの問題は、せいぜい百万円単位。十万円単位の問題である。
国会を一日開けば、かかる費用は、およそ三億円といわれている。国の借金はたまる一方といわれている。日本国は、なにをしているのか。
国会は、なにをやっているのか。マスコミは、なにをやっているのか。目先のことや、部分ばかりを見て全体を見ていない。
落した千円札をさがすために、十人の人をやとうようなことをやっている。人件費のことを考えたならば、話にならないではないか。
かくて、日本国の借金はふえて行く。そのツケは、後の世代の人々にまわされて行く。
人々は、百円、千円、一万円ていどまでのことは、具体的な感覚としてよくわかる。節約意識が働く。しかし、十億、百億、一千億の額になると、具体的な感覚が働かなくなる。なにがなんだかわからなくなる。節約意識が働かなくなる。なくなった考古学者の森浩一ものべている。
「ぼくはこれからも本当の学問は町人学者が生みだすだろうとみてる。官僚学者からは本当の学問は生まれそうもない。」
「今日の政府がかかえる借金は、国立の研究所などに所属するすごい数の官僚学者の経費も原因となっているだろう。」(以上、『季刊邪馬台国』102号、梓書院、2009年刊)
「僕の理想では、学問研究は民間(町)人にまかせておけばよい。国家が各種の研究所などを作って、税金で雇った大勢の人を集めておくことは無駄である。そういう所に勤めていると、つい権威におぼれ、研究がおろそかになる。」(『森浩一の考古交友録』[朝日新聞出版、2013年刊]157ページ)
これは率直にして、かつ、きわめて深刻な意見である。森浩一は、見聞きした経験にもとづく本音をのべている。
このように、厖大な「税金」が「無駄」に費消されている。
心ある考古学者たちは、すでに、発言しているのである。このように、同業の考古学者たちがみても、ひどすぎるのではないかと、眉をひそめる状況が存在している。
考古学に関連する人類学その他の分野の学者も、考古学の世界のあり方について、警報を発している。
旧石器捏造事件がおきたとき、人類学者で、国立科学博物館人類研究部長(東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻教授併任)の馬場悠男(ばばひさお)氏がのべている。
「今回の旧石器遺跡捏造事件に関しては、日本の考古学者たちの特殊な状況が遠因であると推察している。すなわち、高齢あるいは著名な権威者に対する過度の追従、科学的批判精神の不足、下部現場担当者と上部機関研究者との二重構造性、確率統計的な蓋然性と再現性に対する認識不足、などである。」
「考古学界全体として、『年功序列と慎み深い意見発表』ということで、先輩の業績にたいしては批判しないわけです。批判すると、『お前は生意気だ』なんてことになって、先輩から恨まれてしまう。うっかり若いうちに批判すると、永久にまともな職に就けない可能性が大いにあったわけです。」
「批判をするかしないかは自由なのですが、今回みたいに、今までの常識とは整合しない『大発見』によって、列車『前・中期旧石器号』が断崖絶壁に向かっている場合には、手をこまねいていてよいのでしょうか。少なくとも列車から降りて、大声で叫ぶ必要があるでしょうし、できればポイントを切り替えるなり、前に出て止める工夫をすべきだろう、と思います。しかし、そういうことをした考古学者はほとんどいませんでした。」(以上、春成秀爾編『検証・日本の前期旧石器』学生社、2001年刊)
「ストップ詐欺被害!」という警告は詐欺師たちだけのためにあるのではない。一群の考古学者たちは、みずから意識せずに、社会に被害を与える存在となりつつある。
大きな金額が動けば、それを動かすための組織ができる。それを差配する人たちが生まれる。
そしてまた、それを少しでも獲得しようとする人たちがあらわれる。石や土の巨塔が生ずる。
マグマはたまっている。
考古学は、いつ爆発してもおかしくない爆弾をかかえている。
国全体のことを考える人は、声をあげて欲しい。暴走列車のポイントを、できれば切り替えるべく。
日本の考古学は、魑魅魍魎(ちみもうりょう)の百鬼夜行(ひゃっきやぎょう)している世界である。犬の骨とゴキブリのうごめく世界。纒向邪馬台国は、(解釈)捏造の産物である。
・みんなでまちがえる考古学。そこだと思えばそこになる方法。
・邪馬台国畿内説は、不都合なデータや事実は、十分な理由を上げずに、無視または否定することによって成立している。
・「犬の骨」「ゴキブリ」→卑弥呼論、邪馬台国論は、科学でも、学問でもなく、単なる連想解釈論である。
たとえば鏡や勾玉であれば、どの県から出土したとしても記録される可能性がある。
しかし、犬の骨やチャバネゴキブリは、奈良県以外の県から出土したばあいに、記録される可能性は低い。
奈良県にだけ、特別に光をあてて照らしたため、記録された可能性が大きい。他県との比較を伴っていない。
・奈良県のばあい、土器による編年は確実な年代との接点をもたない。推定年代の浮動性が大きい。寺沢薫氏の推定年と関川尚功氏の推定年とは、大きく異なる。
・トランプ流考古学・・・それに従わなければ、生活上、経済上、不利益となる。
・「論点先取(結論を先に決めて議論する)」ばかりで、証明になっていない。
・寺沢薫氏は、「イト国東遷説」の立場に立っている。
二世紀のはじめごろに、北部九州を中心に、イト(伊都)倭国が誕生し、それが三世紀はじめに東遷し、奈良県の纏向遺跡の地に王都建設したという。
そして卑弥呼を共立し、ヤマト王権が誕生したという。
『古事記』『日本書紀』は物部氏の祖の饒速日の命の東遷伝承や、皇室の祖の神武天皇の東遷伝承を記すが、伊都国の東遷、伊都国王のなんという人が東遷したのかなどは、記すところがない。
仮説を立てるならば、『古事記』『日本書紀』の伝承も生かした方が、説得力は大きくなるはずである。
饒速日の命の子孫は、八十(やそ)物部と言われる物部氏や尾張氏として、その後も繁栄する。
神武天皇の子孫は、天皇家として、現代までも続く。
東遷して来たはずの伊都国王の子孫系の氏族は、何なのか?
卑弥呼は誰か。『古事記』『日本書紀』の中に、名を残しているのか否か。
そのようなことが説明できなければ、「イト国東遷説」は、結局は寺沢氏個人が、新たに作った「物語(現代人の創出した神話)」になってしまう。
「考古栄えて記紀滅ぶ」の例がまた一つふえることになる。
「邪馬台国=畿内説」といえば、まず疑ってよい段階に達している。




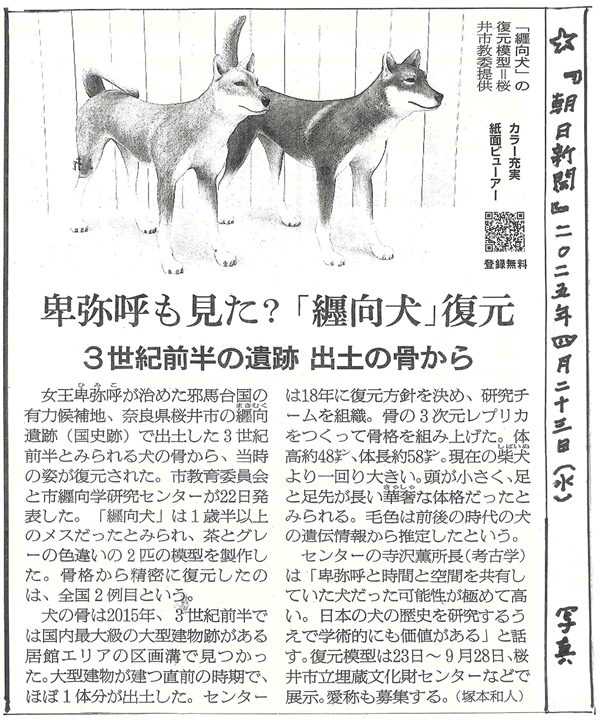
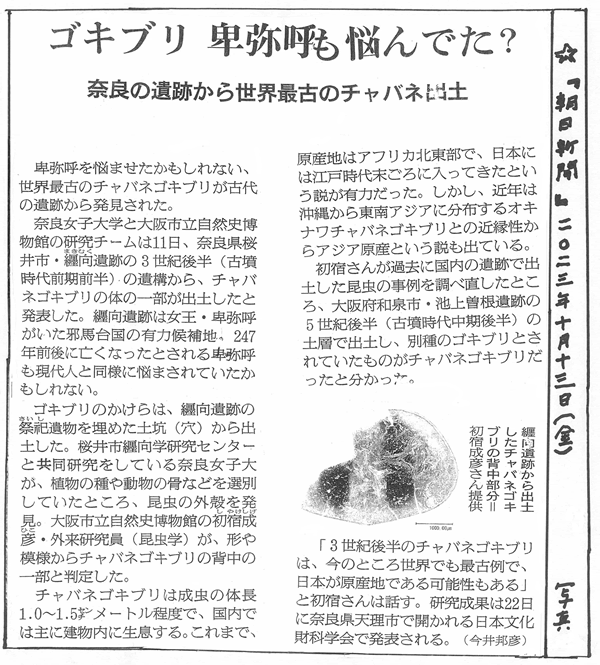
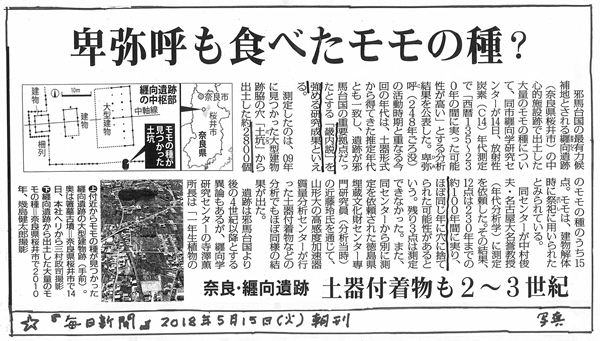
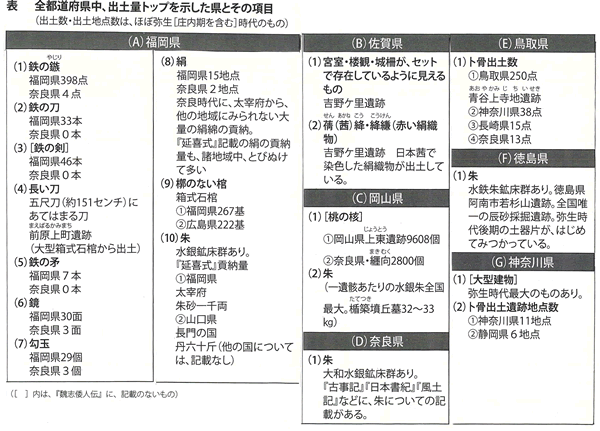
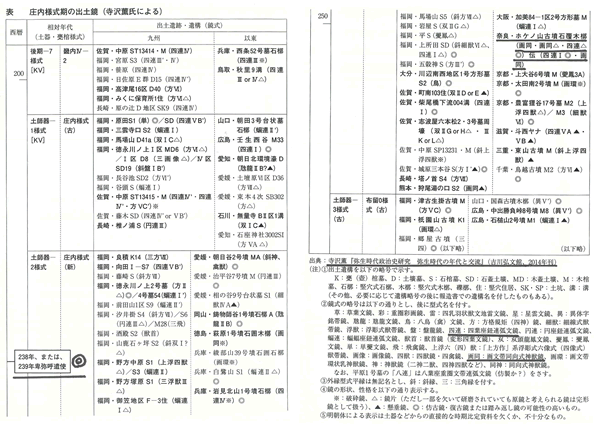
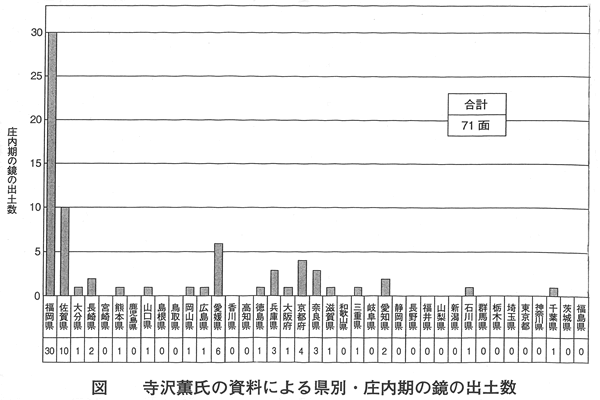
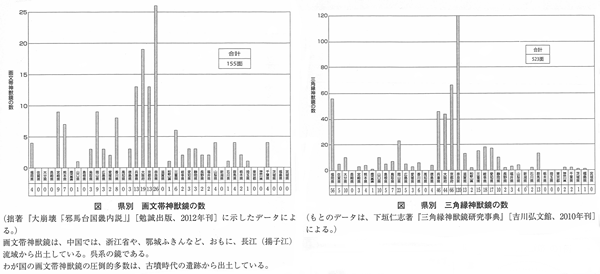
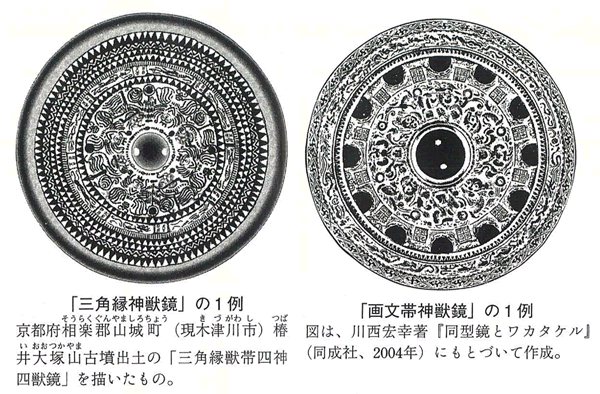
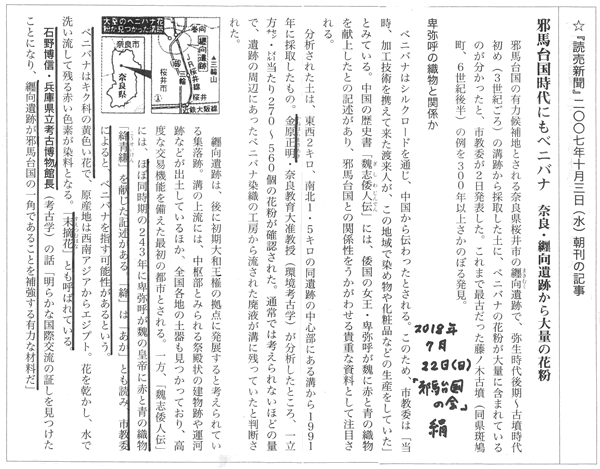
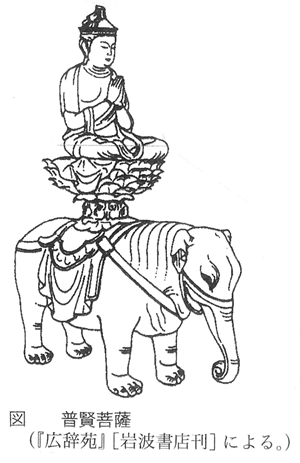 主人公の光源氏は、さる女性の手引きで、「末摘花」という名の女性とあう。
主人公の光源氏は、さる女性の手引きで、「末摘花」という名の女性とあう。