| TOP>活動記録>講演会>第237回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
Rev2 2024.8.12
|
第237回 講演会(2005.9.25 開催) | ||||
1.『魏志倭人伝』の植物
|
魏志倭人伝には、次のような植物が記載されている。
 これらは、現在のどの植物にあたるのか。
これらは、現在のどの植物にあたるのか。
魏使が日本で見た比較的ありふれた植物であったと考えられる。 とすれば、『古事記』『日本書紀』『風土記』『万葉集』などに記載されている植物である可能性が、かなり考えられる。 そこで、これらの日本古典に記されている植物のなかから、『魏志倭人伝』に記されて いる植物の候補になりそうなものを探し出す。 ■ 投(とう) 「『投』は『柀』という字の誤写で、『杉』のことである。」と、明治の東洋学者・那珂通世が述べている。 しかし『日本書紀』では、「杉」は舟の材料、「柀(まき)」は棺の材料と記述され、「杉」と「柀」とは明確に区別されている。 日本では、「まき」の仲間の高野槙(こうやまき)が、平原遺跡の割竹形木棺の例のように、棺材として使われるが、『日本書紀』編纂に関わった中国の学者が、高野槙を、中国の「柀」の仲間と判断した可能性が大きい。 なお、高野槙は、高野山に多く産するスギ科の常緑高木で、世界の中で日本にのみ産する。韓国の扶余出土の木棺に、高野槙が使用されていたことが判明したが、この高野槙は日本と百済の交流の中で日本から移入された可能性が高い。 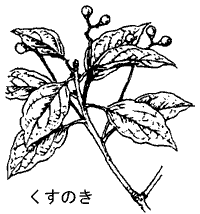
■ 豫樟(よしょう)「クス」 「豫樟」について、『日本書紀』に次のような記述例がある。
 とは、「木へん」がついているかどうかの違いであるが、同じものと
みてよい。日本の古代人は「豫樟」を「クス」と理解していたようだ。 とは、「木へん」がついているかどうかの違いであるが、同じものと
みてよい。日本の古代人は「豫樟」を「クス」と理解していたようだ。
梁の昭明太子の編纂した『文選(もんぜん)』の中に、『魏志倭人伝』とほぼ同じころ成立した、左太沖の「呉都の腑」がおさめられている。このなかの植物についての記述は、型式・内容とも、『魏志倭人伝』によく似ており、「豫樟」なども記されている。 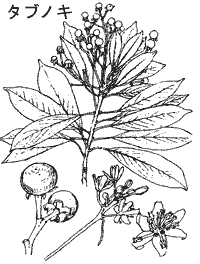 このころの地方誌などの記述には一定のスタイルがあったと想定される。 『文選』を参考にすることによって、同じスタイルで記述された『魏志倭人伝』の植物のことがかなり分かる。 ■  (なん、または、ぜん) (なん、または、ぜん)
「  」はふつうの『文選』の注釈書では「くす」と読まれている。 」はふつうの『文選』の注釈書では「くす」と読まれている。
楩  (べんなん)、あるいは、
楩 (べんなん)、あるいは、
楩 豫樟(べんなんよしょう)
のように熟語的に使用されることがある。 豫樟(べんなんよしょう)
のように熟語的に使用されることがある。
高橋忠彦の『文選中』では、楩・  ・豫樟は、すべて楠の類と記されている。 ・豫樟は、すべて楠の類と記されている。
豫樟が楠なので、  は、クスノキ科の常緑高木「タブノキ」と考えるのが良いであろう。 は、クスノキ科の常緑高木「タブノキ」と考えるのが良いであろう。
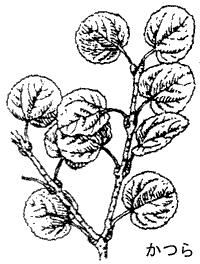 ■ 楓香(ふうこう)
■ 楓香(ふうこう)
「楓」の字は『古事記』に使用例があり、「湯津楓(ゆつかつら)」のように、 「かつら」とよまれ、「湯津香木」とも書かれた。「楓」は「香木」と考えられて いたのである。 『万葉集』でも「楓」は「カツラ」と読まれている。 「かつら」の語源は「香つ(つ:助詞のノの意味)ら(ら:ものの意味)」と推定される。「ら」を「もの」の意味とする例に、「さくら」「もぐら」「まくら」「つらら」などがある。 『広辞苑』で「カツラ」を引くと、二つの説明がある。
 現代の「楓(ふう)」は、中国・台湾が原産で、江戸時代(享保五年ごろ)渡来したという記録がある。「お(雄)かつら」ともいう。
現代の「楓(ふう)」は、中国・台湾が原産で、江戸時代(享保五年ごろ)渡来したという記録がある。「お(雄)かつら」ともいう。
なお、「楓」を「かえで(語源:蛙手)」と読むのは日本でのあてはめのようである。 倭人伝の時代に「楓」と呼ばれたのは、現代の楓(ふう)ではなく、日本の山地に自生する「桂」であろう。「桂」は古来からある日本特産の喬木で、「め(雌)かつら」とも呼ばれる。 「おかつら」も「めかつら」もともに香木である。 |
2.『魏志倭人伝』の動物
|
■ いなかった動物
『魏志倭人伝』には、獮猴(おおざる)、黒雉(きじ)はいるが、牛、馬、かささぎは、いなかったと記述される。 しかし、弥生時代の遺跡からは、牛の骨が出てくる。また、『古事記』の記述には馬が現れるので、牛や馬も日本にはいたという見解もある。牛、馬の存在についてはまだ議論がある。 現在、九州には「かささぎ」がいる。これは豊臣秀吉が朝鮮から持ってきたものといわれている。朝鮮に勝利したときの鳥なので「かちがらす」と呼んだそうである。 |
3.韓国の史跡
|
■ 慶州 仏国寺(ブルクックサ)と石窟庵(ソックルアム)
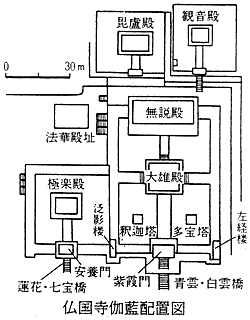 慶州の史跡で見ごたえがあるのは仏国寺と石窟庵。
慶州の史跡で見ごたえがあるのは仏国寺と石窟庵。
仏国寺の開創は新羅第23代法興王の22年(535年)と伝えられているが、 実質的には第35代景徳王10年(751年)に宰相の金大城が、国家の安寧と現世 二親のために、吐含山(トハンサン)の中腹に大伽藍を興したものに始まるものと見られている。 このとき、同時に金大城は前世父母のために吐含山上に石窟庵を開いた。 仏国寺は護国仏教の中心地として栄えた大伽藍だが、兵火その他の災害を受け、木造建築のすべてが李朝時代に中期以降のものに建て変わった。現在の伽藍は、1972に大規模な復元工事が行われ、新羅時代の旧観をよく示しているという。 ■ 武烈王陵と掛陵(クエヌン) 韓国政府は文化財の保護に力を入れており、王陵とされる古墳の治定をしているが、日本の古墳同様、誰の陵墓と指定するのは難しいようだ。そのなかにあって、新羅王第29代の武烈王陵は確実だといわれている。 武烈王陵は三国統一の覇者にふさわしく立派。 ■ 武烈王 『日本書紀』「孝徳天皇紀」大化三年(647年)の条で、高向玄理(黒麻呂)が新羅へ使わされて、新羅の皇子、金春秋を人質として来日させた記述がある。金春秋がのちの武烈王である。 654年に武烈王として即位し、660年に唐と連合して、日本軍を白村江の戦いで破り、百済を滅亡させた。 武烈王の義兄・金  信(きんゆしん)将軍の活躍で、新羅を統一。更には朝鮮半島の統一の基礎をかためた。 信(きんゆしん)将軍の活躍で、新羅を統一。更には朝鮮半島の統一の基礎をかためた。
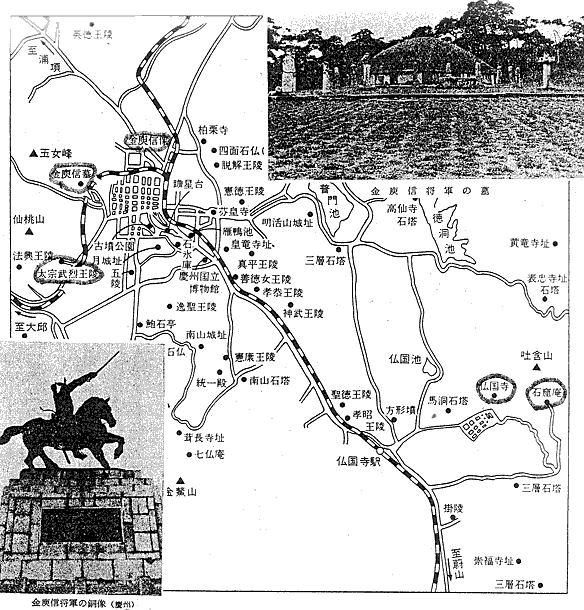
|
| TOP>活動記録>講演会>第237回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |